2015年11月30日
奈良にフィールドワークに行きました2
奈良フィールドワークの続きです。
鹿を求めて、奈良公園に向かう途中で、
興福寺に立ち寄りました。

阿修羅像で知られる興福寺ですが、
現在は、耐震補強をしている建物があります。
東金堂と五重塔は、拝観できるので、
世界遺産に登録されている寺内を散策しました。

ここにも鹿がいました。
表の通りに戻らず、そのまま、鹿について、
裏手の道を歩いていきます。

すると、興福寺を詠った、
会津八一の歌碑がありました。

奈良公園で鹿と戯れて、そのまま、
奈良国立博物館の裏手へ。


国立博物館の裏手にはお庭があり、
八窓庵という茶室が移築されています。
もとは興福寺の庭内にあったものだそうです。

さらに行くと、トトロの子どもが棲んでいそうな、
朽ちた古木の向こうに、
仏教美術資料研究センターが見えてきました。

仏教美術資料研究センターの建物は、もとは、
明治35年に竣工した、奈良県物産陳列所として、
使用用されていたものです。
和風と洋風が混じった、面白い意匠の建築です。

奈良国立博物館では、
「奈良博の庭園・散策マップ」を用意しています。
これを見ながら、歩いてみるのも楽しいですね。

鹿を追って、予定とは違うところを歩きました。
フィールドワークの面白さは、
こういう偶然を楽しむところにあります。

報告:長沼光彦
鹿を求めて、奈良公園に向かう途中で、
興福寺に立ち寄りました。

阿修羅像で知られる興福寺ですが、
現在は、耐震補強をしている建物があります。
東金堂と五重塔は、拝観できるので、
世界遺産に登録されている寺内を散策しました。

ここにも鹿がいました。
表の通りに戻らず、そのまま、鹿について、
裏手の道を歩いていきます。

すると、興福寺を詠った、
会津八一の歌碑がありました。

奈良公園で鹿と戯れて、そのまま、
奈良国立博物館の裏手へ。


国立博物館の裏手にはお庭があり、
八窓庵という茶室が移築されています。
もとは興福寺の庭内にあったものだそうです。

さらに行くと、トトロの子どもが棲んでいそうな、
朽ちた古木の向こうに、
仏教美術資料研究センターが見えてきました。

仏教美術資料研究センターの建物は、もとは、
明治35年に竣工した、奈良県物産陳列所として、
使用用されていたものです。
和風と洋風が混じった、面白い意匠の建築です。

奈良国立博物館では、
「奈良博の庭園・散策マップ」を用意しています。
これを見ながら、歩いてみるのも楽しいですね。

鹿を追って、予定とは違うところを歩きました。
フィールドワークの面白さは、
こういう偶然を楽しむところにあります。

報告:長沼光彦
2015年11月29日
奈良にフィールドワークに行きました 1
本日は、京都を飛び出し、
奈良にフィールドワークに行きました。
(あまり奈良らしくありませんが、
近鉄奈良駅前です。)

3年ゼミの学生が、奈良に興味があるというので、
出かけることにしたのです。
奈良の名物、奈良を詠んだ和歌、
奈良の寺社について、
あらかじめ調べて、ゼミで発表しました。
とりあえず学生が、奈良公園にいる鹿、
について興味があるというので、
近鉄奈良駅より、奈良公園に向かい歩いていきます。

奈良公園の鹿とは言いますが、
元は、春日大社の神の使いとされたものです。
鹿島神宮から武甕槌命(たけみかづちのみこと)が、
御蓋山(みかさやま)まで、白鹿に乗って到来したと言われます。
これが春日大社が創建のきっかけとなりました。
以来、神鹿として保護するようになったということです。

(奈良公園Quick Guide ホームページには、
野生動物としての鹿を紹介した、
リーフレットもあります。
こちらも、読んでみると面白いですよ。)
ひとまず、おきまりで、
鹿せんべいを買って、
鹿に食べてもらいました。

近鉄奈良駅に近い、
奈良公園にいた鹿は、
食べても食べなくても良い、
という態度でした。
ところが、春日大社の方へ行くと、
積極的に鹿せんべいをもらいに来ます。

どうやら、お客さんたちが、
駅に近い方でばかりあげるので、
奥の方の鹿は、比較的食べていないようです。
喜んで食べる様子が見たければ、
春日大社に着くまで、待った方が良いようです。
帰り道、夕方になったときに、
鹿の鳴き声が聞こえました。
「いいーん」という、高い声です。
遠くで聞いているときは、
子どもが声をあげているのかと思ったのですが、
近くで鳴いている鹿を見つけ、
鹿の声だとわかったのです。

(鹿 鳴き声 で検索すると、
youtubeで公開されている音声が見つかります。)
奥山に紅葉踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋は悲しき
という、百人一首の歌を思い出すような、
もの悲しい感じを抱かせる声でした。
報告:長沼光彦
奈良にフィールドワークに行きました。
(あまり奈良らしくありませんが、
近鉄奈良駅前です。)

3年ゼミの学生が、奈良に興味があるというので、
出かけることにしたのです。
奈良の名物、奈良を詠んだ和歌、
奈良の寺社について、
あらかじめ調べて、ゼミで発表しました。
とりあえず学生が、奈良公園にいる鹿、
について興味があるというので、
近鉄奈良駅より、奈良公園に向かい歩いていきます。

奈良公園の鹿とは言いますが、
元は、春日大社の神の使いとされたものです。
鹿島神宮から武甕槌命(たけみかづちのみこと)が、
御蓋山(みかさやま)まで、白鹿に乗って到来したと言われます。
これが春日大社が創建のきっかけとなりました。
以来、神鹿として保護するようになったということです。

(奈良公園Quick Guide ホームページには、
野生動物としての鹿を紹介した、
リーフレットもあります。
こちらも、読んでみると面白いですよ。)
ひとまず、おきまりで、
鹿せんべいを買って、
鹿に食べてもらいました。

近鉄奈良駅に近い、
奈良公園にいた鹿は、
食べても食べなくても良い、
という態度でした。
ところが、春日大社の方へ行くと、
積極的に鹿せんべいをもらいに来ます。

どうやら、お客さんたちが、
駅に近い方でばかりあげるので、
奥の方の鹿は、比較的食べていないようです。
喜んで食べる様子が見たければ、
春日大社に着くまで、待った方が良いようです。
帰り道、夕方になったときに、
鹿の鳴き声が聞こえました。
「いいーん」という、高い声です。
遠くで聞いているときは、
子どもが声をあげているのかと思ったのですが、
近くで鳴いている鹿を見つけ、
鹿の声だとわかったのです。

(鹿 鳴き声 で検索すると、
youtubeで公開されている音声が見つかります。)
奥山に紅葉踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋は悲しき
という、百人一首の歌を思い出すような、
もの悲しい感じを抱かせる声でした。
報告:長沼光彦
2015年11月28日
図書館で開催中の「ぐりとぐら展」
ご存知のように、『ぐりとぐら』は中川李枝子(さく)山脇百合子(え)の絵本です。シリーズで絵本が発行されていますが、シリーズ1作目の『ぐりとぐら』だけで、2015年現在、472万部発行されているそうです。
本学の図書館では今、ラーニングコモンズの入り口付近で、「ぐりとぐら展」という展示が行われています。

少し前に黄色い軍手で手作りしていた「ぐりとぐら」のぬいぐるみに、UVレジンでかわいくリボン型にした「手作りのLED」を付けた作品が、この「ぐりとぐら展」に、飾られています。(これ、LilyPad研究会 作品なのです。)

というフレーズや、「ぐりとぐらを正しく並べた時だけ、LEDが光ること」をクイズ形式で書いて下さっていて感激!
ぐりとぐらのシリーズ本や中川李枝子さんの他の作品が並んでいて、借りることができるのも嬉しいですし、9カ国語に翻訳された「ぐりとぐら」の朗読CDが流れているのも、感動です。図書館に行かれた方は、ぜひ見てくださいね。

報告:吉田智子
本学の図書館では今、ラーニングコモンズの入り口付近で、「ぐりとぐら展」という展示が行われています。

少し前に黄色い軍手で手作りしていた「ぐりとぐら」のぬいぐるみに、UVレジンでかわいくリボン型にした「手作りのLED」を付けた作品が、この「ぐりとぐら展」に、飾られています。(これ、LilyPad研究会 作品なのです。)

ぐりとぐら ぐらとぐりでは 光りません
というフレーズや、「ぐりとぐらを正しく並べた時だけ、LEDが光ること」をクイズ形式で書いて下さっていて感激!
ぐりとぐらのシリーズ本や中川李枝子さんの他の作品が並んでいて、借りることができるのも嬉しいですし、9カ国語に翻訳された「ぐりとぐら」の朗読CDが流れているのも、感動です。図書館に行かれた方は、ぜひ見てくださいね。

報告:吉田智子
2015年11月27日
クリスマスイルミネーションの点灯式を行いました
今日、本学でノートルダムクリスマス イルミネーションの点灯式を行いました。

引き締まった冬の空気の中に、ハンドベルの澄んだ音色が響きました。本学のハンドベル部による〈もみの木〉の演奏の後、Sr.和田理事長が、クリスマスの意味についてお話をされ、「クリスマスは人々の喜びと慰めのために、救い主がこの世に来られた日です。このノートルダムのイルミネーションが道行く人々の喜びと慰めになりますように」としめくくられました。
イルミネーションが点灯されると、再びハンドベル部が〈クリスマスの鐘〉と〈鐘のキャロル〉を演奏し、私たちは耳を傾けました。

本学のイルミネーションはぱあっと目を引く賑やかさはないものの、優しく上品な雰囲気を漂わせています。近くにお越しの際には、ぜひご覧ください。

報告:岩崎れい

引き締まった冬の空気の中に、ハンドベルの澄んだ音色が響きました。本学のハンドベル部による〈もみの木〉の演奏の後、Sr.和田理事長が、クリスマスの意味についてお話をされ、「クリスマスは人々の喜びと慰めのために、救い主がこの世に来られた日です。このノートルダムのイルミネーションが道行く人々の喜びと慰めになりますように」としめくくられました。
イルミネーションが点灯されると、再びハンドベル部が〈クリスマスの鐘〉と〈鐘のキャロル〉を演奏し、私たちは耳を傾けました。

本学のイルミネーションはぱあっと目を引く賑やかさはないものの、優しく上品な雰囲気を漂わせています。近くにお越しの際には、ぜひご覧ください。

報告:岩崎れい
2015年11月26日
にわかに寒くなりました
本日、京都は急に気温がさがりました。
全国的に、冬型の気圧配置になったようです。

とはいえ、まだキャンパスの紅葉は、
赤く染まりきってはいません。
もう少し寒い日が続いたら、
色が変わるのでしょう。

そんな冷え込んだ夜ですが、
本日も、図書館では、
学生の皆さんが勉強をしておりました。
(写真は別の時の撮影ですので、
誰も映ってませんが。)

そろそろ、卒業論文の締め切りが近い、
ということもあります。

私も、チェックした卒論の原稿を、
ゼミの学生にお返ししました。

報告:長沼光彦
2015年11月25日
ご利益を求めて河合神社を詣でました
私の担当する、1年次ゼミ、基礎演習では、
神社のご利益について調べています。

今回は、大学の近く、下鴨神社の摂社、
河合神社にフィールドワークに、
出かけました。

摂社とは、本社(この場合下鴨神社)にゆかりのある神を、
境内または境外にまつった神社のことです。

河合神社は、神武天皇の御母神、
玉依姫命(たまよりひめのみこと)を祭神としています。
神社前の案内板によれば、
玉依姫の美麗にあやかり、
自分の顔を絵馬に描き奉納する、
とあります。

手鏡の形をした絵馬に、
顔が書いてあるのですが、
そこに書き加えて、
自分の顔らしく書き上げて、
奉納するのです。
それぞれ、個性のある絵で、
これを拝見するだけでも、
なかなか楽しい感じです。
それぞれが思いを重ねて、
ご利益をいただく。
現代の神様との関わり方が、
見えてきます。

昔の絵馬は、もっと大きく、
看板のような大きさで、
村を代表して捧げるようなものでした。
さらに昔は、本物の馬を、
ささげていました。
報告:長沼光彦
神社のご利益について調べています。

今回は、大学の近く、下鴨神社の摂社、
河合神社にフィールドワークに、
出かけました。

摂社とは、本社(この場合下鴨神社)にゆかりのある神を、
境内または境外にまつった神社のことです。

河合神社は、神武天皇の御母神、
玉依姫命(たまよりひめのみこと)を祭神としています。
神社前の案内板によれば、
玉依姫の美麗にあやかり、
自分の顔を絵馬に描き奉納する、
とあります。

手鏡の形をした絵馬に、
顔が書いてあるのですが、
そこに書き加えて、
自分の顔らしく書き上げて、
奉納するのです。
それぞれ、個性のある絵で、
これを拝見するだけでも、
なかなか楽しい感じです。
それぞれが思いを重ねて、
ご利益をいただく。
現代の神様との関わり方が、
見えてきます。

昔の絵馬は、もっと大きく、
看板のような大きさで、
村を代表して捧げるようなものでした。
さらに昔は、本物の馬を、
ささげていました。
報告:長沼光彦
2015年11月24日
入院中の子どもたちへのお話会
ご報告が遅くなりましたが、9月24日に、小児医療プログラムの実践講座に今年度参加している学生が入院中の子どもたちにお話会を実施しました。これは、京都府立医科大学との連携プログラムのひとつとして本学が実施しているもので、子どもの発達と遊び、病児の学習支援、グリーフケアなどに関する基礎講座を受講したあと、希望する学生が参加する講座で、入院している子どもたちにお話会をしたり、院内学級の先生方のお手伝いをしたりする取り組みです。

今回は、人間文化学部人間文化学科と心理学部の学生が参加し、大型絵本を使って『はらぺこあおむし』『だるまさんが』の読み聞かせをしました。

「キャベツーの、なかかーら」と手遊びをしたり、あおむしとだるまさんのペープサートを使ったりするなど、学生たち自身が考えた工夫が随所に見られ、また、参加学生がそれぞれ放送部と演劇部に所属していることもあって、声も張りがあって生き生きとしていました。

参加してくれた子どもたちは、初め恥ずかしがっていましたが、後半に入ると一緒に手を動かしたり、声を出してくれたりしました。お母さんのお膝に頭を乗せながら、聞いてくれた子が、終わった時に「(終わるのが)早い」と言ってくれたりもしましたので、学生も嬉しかったのではないかと思います。

治療や体調との関係でお話会に参加できない子どもたちもいますので、学生は参加できない子の分のおみやげも毎回作ります。今回は、学生の描いただるまさんの絵のしおりをラミネートしたものでした。場合によっては長く入院し、つらい治療と向き合うことの多い子どもたちに、自分たちが学んだことをもとに工夫して、ささやかな楽しみを提供できること、そのような機会は、学生にとって貴重で意義のある体験になっています。
報告:岩崎れい
※京都府立医科大学との連携プログラムの紹介はこちらをご覧下さい。
https://www.notredame.ac.jp/cooperation/hospital/

今回は、人間文化学部人間文化学科と心理学部の学生が参加し、大型絵本を使って『はらぺこあおむし』『だるまさんが』の読み聞かせをしました。

「キャベツーの、なかかーら」と手遊びをしたり、あおむしとだるまさんのペープサートを使ったりするなど、学生たち自身が考えた工夫が随所に見られ、また、参加学生がそれぞれ放送部と演劇部に所属していることもあって、声も張りがあって生き生きとしていました。

参加してくれた子どもたちは、初め恥ずかしがっていましたが、後半に入ると一緒に手を動かしたり、声を出してくれたりしました。お母さんのお膝に頭を乗せながら、聞いてくれた子が、終わった時に「(終わるのが)早い」と言ってくれたりもしましたので、学生も嬉しかったのではないかと思います。

治療や体調との関係でお話会に参加できない子どもたちもいますので、学生は参加できない子の分のおみやげも毎回作ります。今回は、学生の描いただるまさんの絵のしおりをラミネートしたものでした。場合によっては長く入院し、つらい治療と向き合うことの多い子どもたちに、自分たちが学んだことをもとに工夫して、ささやかな楽しみを提供できること、そのような機会は、学生にとって貴重で意義のある体験になっています。
報告:岩崎れい
※京都府立医科大学との連携プログラムの紹介はこちらをご覧下さい。
https://www.notredame.ac.jp/cooperation/hospital/
タグ :小児医療プログラム
2015年11月23日
「明日になれば」上映会にお出でいただき、ありがとうございます。
本日、本学にて、
梅若ソラヤ監督「明日になれば」上映会を、
開催しました。
多くのご来場ありがとうございます。

映画は、現在のレバノンで活躍する、
アーティストの話を中心に、
構成されたドキュメンタリーです。

レバノンというと、
1975年に始まる内戦のイメージが強いかと思います。
アーティストの話の中には、
近年まで続いた、内戦や戦争の影は現れます。
一方で、現在を生きる姿、表現する生き方が、
アーティストの話と、映像の構成によって、
立ち現れてきます。

その異文化の魅力と、レバノンに生きる人たちの活気に、
心動かれた学生もいたようです。

これを機会に、中東の多様な姿に、
興味を持ってもらえると良いですね。
報告:長沼光彦
梅若ソラヤ監督「明日になれば」上映会を、
開催しました。
多くのご来場ありがとうございます。

映画は、現在のレバノンで活躍する、
アーティストの話を中心に、
構成されたドキュメンタリーです。

レバノンというと、
1975年に始まる内戦のイメージが強いかと思います。
アーティストの話の中には、
近年まで続いた、内戦や戦争の影は現れます。
一方で、現在を生きる姿、表現する生き方が、
アーティストの話と、映像の構成によって、
立ち現れてきます。

その異文化の魅力と、レバノンに生きる人たちの活気に、
心動かれた学生もいたようです。

これを機会に、中東の多様な姿に、
興味を持ってもらえると良いですね。
報告:長沼光彦
2015年11月22日
11月23日 映画「明日になれば」上映会・監督トークショー
レバノンのドキュメンタリー映画
「明日になれば」の上映会ならびに監督トークショー
が、2015年11月23日(月・祝)、明日になりました。
本学大学院人間文化研究科人間文化専攻
開設10周年記念事業として開催します。
映画:「明日になれば」 2013年/アラビア語、英語/
字幕あり(日本語、英語)/70分
出演:ベルナード・フーリー、サイード・アイル、アリサール・カラカッラ
監督・プロデューサー:梅若ソラヤ
日時:2015年11月23日 (月・祝) 16:30-18:30(受付開始:16:00)
会場:京都ノートルダム女子大学 ユージニア館3階 NDホール
参加対象者:一般の方および本学学生
入場無料・申込不要
後援 京都新聞
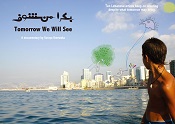
レバノンはキリスト教、イスラム教を主とした18の宗教宗派が
入り混じったモザイク国家とよく言われます。そんなレバノンに住む
10人のアーティストが不安定な政情のなかで自らの芸術にかける
姿を追ったドキュメンタリーが上映作品です。ナショナル・
ジオグラフィック映画祭とモントリオールの国際芸術映画祭(FIFA)
で上映されました。東京の各地でも上映され好評でした。
関西では初の上映となります。

私が監督である梅若ソラヤさんのお母様を存じ上げており、
お母様から是非関西で「明日になれば」を上映したいという
ご希望を伺い、今回、東京在住のソラヤさんを招いて
上映会・監督トークショーの企画が実現することになりました。

梅若ソラヤさんはドキュメンタリー映画作家です。
日本人の父とレバノン人の母の間に生まれました。
『ストリート・ウィットネス』(エクアドル/2007年)、
『私は幸せ』(ブラジル/2010年)を制作されています。
『明日になれば』はデンマークのテレビ局によっても
放映が行われました。

映画の上映後、梅若監督による映画制作の意図、舞台裏などを語る
トークショーも行います。トークショーでは会場からの質問もお受けし、
日本では知る機会の少ないレバノンの状況や芸術についての理解を
参加者に深めていただきたいと考えています。
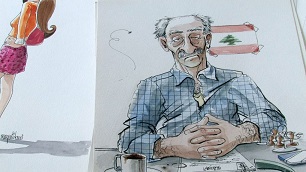
みなさん、どうかふるってご参加ください。
本学大学院人間文化研究科人間文化専攻・人間文化学部人間文化学科
鷲見朗子(すみ あきこ)
(このブログは、10月20日に案内したものの再録です。)
「明日になれば」の上映会ならびに監督トークショー
が、2015年11月23日(月・祝)、明日になりました。
本学大学院人間文化研究科人間文化専攻
開設10周年記念事業として開催します。
映画:「明日になれば」 2013年/アラビア語、英語/
字幕あり(日本語、英語)/70分
出演:ベルナード・フーリー、サイード・アイル、アリサール・カラカッラ
監督・プロデューサー:梅若ソラヤ
日時:2015年11月23日 (月・祝) 16:30-18:30(受付開始:16:00)
会場:京都ノートルダム女子大学 ユージニア館3階 NDホール
参加対象者:一般の方および本学学生
入場無料・申込不要
後援 京都新聞
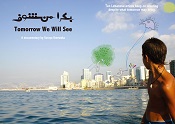
レバノンはキリスト教、イスラム教を主とした18の宗教宗派が
入り混じったモザイク国家とよく言われます。そんなレバノンに住む
10人のアーティストが不安定な政情のなかで自らの芸術にかける
姿を追ったドキュメンタリーが上映作品です。ナショナル・
ジオグラフィック映画祭とモントリオールの国際芸術映画祭(FIFA)
で上映されました。東京の各地でも上映され好評でした。
関西では初の上映となります。

私が監督である梅若ソラヤさんのお母様を存じ上げており、
お母様から是非関西で「明日になれば」を上映したいという
ご希望を伺い、今回、東京在住のソラヤさんを招いて
上映会・監督トークショーの企画が実現することになりました。

梅若ソラヤさんはドキュメンタリー映画作家です。
日本人の父とレバノン人の母の間に生まれました。
『ストリート・ウィットネス』(エクアドル/2007年)、
『私は幸せ』(ブラジル/2010年)を制作されています。
『明日になれば』はデンマークのテレビ局によっても
放映が行われました。

映画の上映後、梅若監督による映画制作の意図、舞台裏などを語る
トークショーも行います。トークショーでは会場からの質問もお受けし、
日本では知る機会の少ないレバノンの状況や芸術についての理解を
参加者に深めていただきたいと考えています。
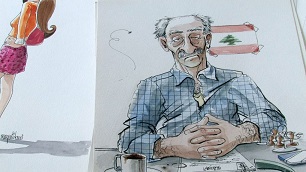
みなさん、どうかふるってご参加ください。
本学大学院人間文化研究科人間文化専攻・人間文化学部人間文化学科
鷲見朗子(すみ あきこ)
(このブログは、10月20日に案内したものの再録です。)
2015年11月21日
出張講義に行ってきました
兵庫県立星陵高校に出張講義に行ってきました。JR垂水駅から山側に上がった高台にあり、正面玄関のたたずまいや校舎が豪壮で美しい学校でした。同校進路指導部長 中村博行先生とは、30年以上にわたる友人で、そのお招きを受けました。
同校には立派な同窓会館もあり、そのホールで、2年生約80名を対象に「日本年中行事研究―生活の中の伝統文化を再発見する」と題し、60分の講義を行いました。「専門家の講義(文科系)」をしてほしいという趣旨でしたので、まずは、文科系の学びの大切さを力説しました。昨今、文科省の通知で話題になっている「文科系不要論」は間違いですよ、これからますます文科系が重要なのですよ、と、我が田に水を引いた次第です。

その後、日本の年中行事が“クールジャパン”の一つであるという視点から、そのおもしろさ、文化としての貴重さ、歴史の古さを具体的に語りました。
講義が始まったのが午後4時だったので、一日の疲れで居眠りを誘ってはいけないと思い、できるだけ多くの質問を発し、フロアに下りて、生徒さんたちとのコミュニケーションを取ることに努めました。
すると、一人の男子生徒・K君が、挙手をしていろいろなことを語ってくれました。
Q しめ縄は何のために張るのですか? K君 神様をお迎えするために張るのです。
Q 正月に使う祝い箸の特徴は何ですか? K君 自分の家では、正月3ヶ日は洗いません。
Q どんなお雑煮を食べていますか? K君 自分の家では焼き穴子を入れて出汁を取ります。
などなど、積極的に授業に参加してくれ、楽しいセッションとなりました。

おかげで、無事60分の講義を終えることができました。終了後には3人の生徒さんが質問に来ました。熱心に講義を聴いてくれたからこそ、質問までしに来ててくれたのでしょう。
全国の高校生諸君、リクエストがあれば、わが学科教員は、どこへでも出張講義に行きますので、ご遠慮なくどうぞ。
〈報告者:堀勝博〉
同校には立派な同窓会館もあり、そのホールで、2年生約80名を対象に「日本年中行事研究―生活の中の伝統文化を再発見する」と題し、60分の講義を行いました。「専門家の講義(文科系)」をしてほしいという趣旨でしたので、まずは、文科系の学びの大切さを力説しました。昨今、文科省の通知で話題になっている「文科系不要論」は間違いですよ、これからますます文科系が重要なのですよ、と、我が田に水を引いた次第です。

その後、日本の年中行事が“クールジャパン”の一つであるという視点から、そのおもしろさ、文化としての貴重さ、歴史の古さを具体的に語りました。
講義が始まったのが午後4時だったので、一日の疲れで居眠りを誘ってはいけないと思い、できるだけ多くの質問を発し、フロアに下りて、生徒さんたちとのコミュニケーションを取ることに努めました。
すると、一人の男子生徒・K君が、挙手をしていろいろなことを語ってくれました。
Q しめ縄は何のために張るのですか? K君 神様をお迎えするために張るのです。
Q 正月に使う祝い箸の特徴は何ですか? K君 自分の家では、正月3ヶ日は洗いません。
Q どんなお雑煮を食べていますか? K君 自分の家では焼き穴子を入れて出汁を取ります。
などなど、積極的に授業に参加してくれ、楽しいセッションとなりました。

おかげで、無事60分の講義を終えることができました。終了後には3人の生徒さんが質問に来ました。熱心に講義を聴いてくれたからこそ、質問までしに来ててくれたのでしょう。
全国の高校生諸君、リクエストがあれば、わが学科教員は、どこへでも出張講義に行きますので、ご遠慮なくどうぞ。
〈報告者:堀勝博〉
2015年11月20日
丸善で檸檬を見た
ある雨の夜、同僚の先生の車で御池まで送っていただいた。そこから四条まで歩いて河原町通を下がっていく途中、三条にあるBALといふビルの建て替へ工事が終はり、そこに丸善(書店)が復活してゐたことを知った。
今をさかのぼること40年ほど前、学生だった頃に訪れて以来だったので、懐かしくなり、立ち寄ってみることにした。昔と違ひ、店は地下に入ってゐた。

地下に向かふエレベータの中で一つの想念が生まれた。きっと、店内に檸檬(レモン)が飾ってあるに違ひない、探してみようと。店に入るや、すぐにその想念どほりに、檸檬が飾ってあるのを見出し、変にくすぐったい気持ちがした。籠の中に、二つの檸檬が仲良く鎮座してゐたのだ。

それを見た私は、一応満足はしたものの、一抹の物足りなさを禁じえなかった。それら黄金色の紡錘形が、カーンと冴えかへってはゐなかったからだ。檸檬はすべからく積み上げた本の上に置いてほしかったのである。
〈堀 記〉
今をさかのぼること40年ほど前、学生だった頃に訪れて以来だったので、懐かしくなり、立ち寄ってみることにした。昔と違ひ、店は地下に入ってゐた。

地下に向かふエレベータの中で一つの想念が生まれた。きっと、店内に檸檬(レモン)が飾ってあるに違ひない、探してみようと。店に入るや、すぐにその想念どほりに、檸檬が飾ってあるのを見出し、変にくすぐったい気持ちがした。籠の中に、二つの檸檬が仲良く鎮座してゐたのだ。

それを見た私は、一応満足はしたものの、一抹の物足りなさを禁じえなかった。それら黄金色の紡錘形が、カーンと冴えかへってはゐなかったからだ。檸檬はすべからく積み上げた本の上に置いてほしかったのである。
〈堀 記〉
2015年11月19日
切り拓く人
4年生の就活の体験を聞いていると、
切り拓いているな、と感じます。

切り拓く、というのは、
開拓する、挑戦して新しい世界を見つける、
という意味です。

大学生活と、社会生活は、
質の異なるステージです。
例えば、人間関係、
責任ということの意味合いが、
全く異なります。

大学では、受け入れがたいことがあれば、
関係を閉じてしまうこともできるでしょう。
しかし、社会では、気が進まなくとも、
いろいろな人とつながって活動していくことになります。
(であれば、こういう人とのつながりを、
肯定的に受け止めて、楽しめる人の方が、
社会生活に向いていることになります。)
就活は、
そういう異なるステージでやっていける自分を、
また、そういう自分になる意思を、
会社に対して示すものです。

自分の踏み入れたことのないステージに、
踏み込む気構えを持つ必要があります。
内定をもらった人の話を聞くと、
そういう気構えを感じます。
新しい世界を切り拓いているな、
と思うわけです。
切り拓いた体験は、
人から教えられたことではなく、
自分で得たものです。
だからこそ、その後の自信にもつながります。
切り拓いた人には、
自分に対する信頼を持つ、
落ち着きが感じられます。

報告:長沼光彦
切り拓いているな、と感じます。

切り拓く、というのは、
開拓する、挑戦して新しい世界を見つける、
という意味です。

大学生活と、社会生活は、
質の異なるステージです。
例えば、人間関係、
責任ということの意味合いが、
全く異なります。

大学では、受け入れがたいことがあれば、
関係を閉じてしまうこともできるでしょう。
しかし、社会では、気が進まなくとも、
いろいろな人とつながって活動していくことになります。
(であれば、こういう人とのつながりを、
肯定的に受け止めて、楽しめる人の方が、
社会生活に向いていることになります。)
就活は、
そういう異なるステージでやっていける自分を、
また、そういう自分になる意思を、
会社に対して示すものです。

自分の踏み入れたことのないステージに、
踏み込む気構えを持つ必要があります。
内定をもらった人の話を聞くと、
そういう気構えを感じます。
新しい世界を切り拓いているな、
と思うわけです。
切り拓いた体験は、
人から教えられたことではなく、
自分で得たものです。
だからこそ、その後の自信にもつながります。
切り拓いた人には、
自分に対する信頼を持つ、
落ち着きが感じられます。

報告:長沼光彦
2015年11月18日
夜までがんばっている学生もいます
本日夜8時過ぎに、そろそろ帰ろうと、
校門に向かったところ、
学生の一団が集っていました。

合唱部の皆さんでした。
定期演奏会に向けて、
練習をしていて、遅くなったのだそうです。

本学はカトリック大学ですので、
行事の際には、
合唱部の皆さんが、賛美歌を歌い、
美声を届けてくれます。
そして、学校行事また別に、
サークル活動として、
演奏会も行うわけです。
日程を紹介しますので、
ぜひ皆様もおいでください。
京都ノートルダム女子大学女声合唱団
第49回定期演奏会
日程:12月26日(土) 開場14:00 開演14:30
会場:ウィングス京都2Fイベントホール(京都市中京区東洞院通六角下る)
縁あってか、
私の担当する基礎演習やゼミにいらした学生が、
合唱団に所属しています。
今は卒業したゼミの学生で、
合唱団に所属していた方もいました。
もちろん、人間文化だけでなく、
大学の各学部学科の学生が参加しています。
京都ノートルダム女子大学の、
伝統あるサークルです。
よろしければ、
この歌声に耳を傾ける機会を持っていただけると幸いです。
報告:長沼光彦
校門に向かったところ、
学生の一団が集っていました。

合唱部の皆さんでした。
定期演奏会に向けて、
練習をしていて、遅くなったのだそうです。

本学はカトリック大学ですので、
行事の際には、
合唱部の皆さんが、賛美歌を歌い、
美声を届けてくれます。
そして、学校行事また別に、
サークル活動として、
演奏会も行うわけです。
日程を紹介しますので、
ぜひ皆様もおいでください。
京都ノートルダム女子大学女声合唱団
第49回定期演奏会
日程:12月26日(土) 開場14:00 開演14:30
会場:ウィングス京都2Fイベントホール(京都市中京区東洞院通六角下る)
縁あってか、
私の担当する基礎演習やゼミにいらした学生が、
合唱団に所属しています。
今は卒業したゼミの学生で、
合唱団に所属していた方もいました。
もちろん、人間文化だけでなく、
大学の各学部学科の学生が参加しています。
京都ノートルダム女子大学の、
伝統あるサークルです。
よろしければ、
この歌声に耳を傾ける機会を持っていただけると幸いです。
報告:長沼光彦
2015年11月17日
卒論を読む
4年生は、大学生活の集大成として、
就活もがんばりますが、
卒論を仕上げるためにも努力します。

本学では、12月が提出締め切りですので、
今頃が仕上げるために一番忙しい時期です。
そんなわけで、教員の私は、
この時期に卒論の草稿をたくさん読むことになります。

仕上がれば18000字くらいの文章を、
ゼミの学生の人数分読むことになります。
なかなかの量ですが、
それだけ読むことができるということは、
ゼミ生の仕事がそれだけ進んでいるということです。

この時期は、読むものがなくて暇であるよりは、
たいへんなくらいの方が、
ゼミ生の努力が目に見える形になっているということです。
報告:長沼光彦
2015年11月16日
話し合うこと
本学に入学してくる学生の皆さんは、
相手を尊重する美質を備えています。
人に無理強いするようなことはしません。

一方で、話し合いの場になると、
遠慮がちになることもあります。
人に意見を押しつけるような気がして、
一歩さがるのかもしれません。

けれども、話し合いの場は、
お互いの話を聞く機会です。
一方的にどちらかの話を聞く場でも、
競ってどちらかが勝つ場でも、
ありません。

意見をうまく伝える表現力が必要であり、
人の意見を理解する力も必要です。

そこで、様々な意見を組み合わせることができれば、
より創造的なアイデアが生まれます。

人間文化学科は、基礎演習や日本語コミュニケーションで、
グループワークを大切にしているのは、
そういう創造的になる機会を、
1年生から作ってほしいからです。

報告:長沼光彦
相手を尊重する美質を備えています。
人に無理強いするようなことはしません。

一方で、話し合いの場になると、
遠慮がちになることもあります。
人に意見を押しつけるような気がして、
一歩さがるのかもしれません。

けれども、話し合いの場は、
お互いの話を聞く機会です。
一方的にどちらかの話を聞く場でも、
競ってどちらかが勝つ場でも、
ありません。

意見をうまく伝える表現力が必要であり、
人の意見を理解する力も必要です。

そこで、様々な意見を組み合わせることができれば、
より創造的なアイデアが生まれます。

人間文化学科は、基礎演習や日本語コミュニケーションで、
グループワークを大切にしているのは、
そういう創造的になる機会を、
1年生から作ってほしいからです。

報告:長沼光彦
2015年11月15日
土曜日の大学
土曜日や日曜日でも、
大学では授業やイベントが
行われることがあります。

例えば、前にご紹介した、
オープンキャンパスも日曜日に行われます。

今は、入学を検討されている方が
いらっしゃる場合は、
キャンパスをご案内しすることもあります。

昨日の土曜日は、
大学院の説明会が行われました。

また、カトリック教育センターが主催する、
土曜公開講座、
「キリスト教とワイン」が開かれました。
担当したのは、人間文化学科の、
シスター中里郁子です。

また、補講や、特別授業が行われることもあります。
イベントが行われる際には、
皆様もぜひおいでください。

報告:長沼光彦
2015年11月14日
食堂でゆったりしてみる
食堂は、もちろん食事をするところですが、
以前お話したように、
忙しい学生の皆さんと話す場にもなります。

また、昼休みの賑わいを避ければ、
ゆったりと過ごすこともできます。

例えば、この中庭が見える場所。
噴水を眺めながら、食事をすると、
カフェテラスで過ごしているような気分になります。
(おそばは、ちょっと似合わなかったかもしれませんが。)


日替わりメニューの、ビーフシューや、
クリームパスタなど、
お好みでどうぞ。


いっそのこと、外に出てみるのもいいでしょう。
さわやかな風の中で、お食事する人もいます。

報告:長沼光彦
2015年11月13日
花のある大学 十六
秋色に染まりつつあるキャンパスですが、
探してみると、お花が見つかります。

赤く染まった桜の葉が散る茶室の前には、
かわいらしい花を見つけることができます。


ユージニア館の前には、
薔薇が一輪咲いています。

ソフィア館の中には、
華道部のお花が飾られています。

報告:長沼光彦
2015年11月12日
創造性を育てること
ただいま、1年次ゼミ基礎演習は、
年度末の発表に向けて準備をしています。

創造性を発揮してほしくて、
自分のアイデアで、
好きなようにしていいんですよ、
などと言うのですが、
自由にすることは、わりと難しいようです。
困難を感じるのは、創造性が、
いつもと違うことをすることだからでしょう。
人間は、だいたい、
日々同じことをしている方が楽です。

すでにわかっていることを繰り返す方が、
やり方もわかっており、
ゴールが見えやすいからです。
創造するということは、
いつもと違うことをすることです。
そこに、新しい自分の発見があります。
自分が変われば、
世界の見え方も変わってきます。
これは、昨日お話ししたこと、
ともつながってきます。

新しい自分を発見することに、
チャレンジする。
そんな活動を始めてもらうために、
身の回りで発見をしようという、
ワークショップもしています。
報告:長沼光彦
2015年11月11日
物故者追悼ミサがありました
本日は午前中に、大学関係者の、
物故者追悼ミサが行われました。

本日いらしていただいた
神父様のお言葉によると、
帰天された方々を思うことは、
私たちがこの場に集ったこと、
また、その方々や周囲の人達との、
つながりを確かめる機会になる、
ということです。

ここからは私の感想です。
私たちは、普段、自分の意思で行動している、
と思っています。
しかし、人との出会いやつながりは、
自分の思いどおりになるわけではありません。
また、思い通りにならないからこそ、
嬉しい意外な出会いがあります。
意外な出会いは、自分を新しい世界に誘い、
成長させてくれます。
神父様の言葉を、
自分自身が変わることで、
今の自分ある場所より、生きる世界を広げる。
そういう人とのつながりを、
ありがたく思うということと解しました。

一方、人とのつながりを大切にしているつもりで、
人との関係を損なう場合もあります。
あいつおせっかいだな、と言われる場合です。
それは、実は、
相手との関係を重んじているのではなく、
自分のしたいことを優先しているからだろう、
と思います。
自分の良いと思っていることが、
相手にとって、また、より多くの人にとって、
良いこととはかぎりません。
自分を信じている人は、
自分の良いことが、世界の良いことと、
思う場合があるようです。
そういう思いこみは、
人とのつながりを重んじているようで、
実際は、自分を相手に押しつけていることになるでしょう。
そんなときに、神父様の言葉にあったように、
一時、自分の立場を離れて、
多くの人とのつながりに目を向けてみると、
おせっかいだったかな、と思い直せるような気がします。
神様を思うということは、
圧倒的に自分と異なる存在を思うことで、
自分の至らなさに気づく、ということではないでしょうか。

私自身が、普段、
それほど人とのつながりを、人の思いを、
優先できているかというと、
なかなか難しいことです。
だからこそ、ミサを機会に、
時にはそんなことを思ってみるのも、
良いのではないかと振り返りました。

報告:長沼光彦
物故者追悼ミサが行われました。

本日いらしていただいた
神父様のお言葉によると、
帰天された方々を思うことは、
私たちがこの場に集ったこと、
また、その方々や周囲の人達との、
つながりを確かめる機会になる、
ということです。

ここからは私の感想です。
私たちは、普段、自分の意思で行動している、
と思っています。
しかし、人との出会いやつながりは、
自分の思いどおりになるわけではありません。
また、思い通りにならないからこそ、
嬉しい意外な出会いがあります。
意外な出会いは、自分を新しい世界に誘い、
成長させてくれます。
神父様の言葉を、
自分自身が変わることで、
今の自分ある場所より、生きる世界を広げる。
そういう人とのつながりを、
ありがたく思うということと解しました。

一方、人とのつながりを大切にしているつもりで、
人との関係を損なう場合もあります。
あいつおせっかいだな、と言われる場合です。
それは、実は、
相手との関係を重んじているのではなく、
自分のしたいことを優先しているからだろう、
と思います。
自分の良いと思っていることが、
相手にとって、また、より多くの人にとって、
良いこととはかぎりません。
自分を信じている人は、
自分の良いことが、世界の良いことと、
思う場合があるようです。
そういう思いこみは、
人とのつながりを重んじているようで、
実際は、自分を相手に押しつけていることになるでしょう。
そんなときに、神父様の言葉にあったように、
一時、自分の立場を離れて、
多くの人とのつながりに目を向けてみると、
おせっかいだったかな、と思い直せるような気がします。
神様を思うということは、
圧倒的に自分と異なる存在を思うことで、
自分の至らなさに気づく、ということではないでしょうか。

私自身が、普段、
それほど人とのつながりを、人の思いを、
優先できているかというと、
なかなか難しいことです。
だからこそ、ミサを機会に、
時にはそんなことを思ってみるのも、
良いのではないかと振り返りました。

報告:長沼光彦



