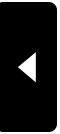2015年07月11日
ラジオ放送生出演!
これまで、話しことばゼミによる
学生企画の、ラジオ番組生出演について、
本ブログでお伝えしてきました。
http://notredameningen.kyo2.jp/e468539.html
http://notredameningen.kyo2.jp/e465043.html
いよいよ本番当日の7月11日。
本番前に皆で集まって最終の打ち合わせをし、



そして本番の13:04を迎えました。
第1部の「ことばアンテナ」も
第2部の「あなたの青春 Music Travel」も、
それぞれの持ち味を十二分に発揮しての放送であったと思います。
放送を終えたばかりのメンバーに、
生放送出演の感想を聞いてみました。
小坂「始まる前はとても緊張していたけど、
ラジオが始まってみれば、
さっきまでのドキドキはどこかに消え、
話すのが楽しい!
というワクワクした気持ちになっていました。」
ドキドキからワクワク・・・
同じ緊張感でも、とても楽しい緊張感でしたね。

川崎「スタジオに入って、
ヘッドフォンをつけてから
緊張がピークになって、
少しでも落ち着くために、
メンバーで
「ゆっくり、元気よく、自信をもって!!」と
何回もつぶやきました。
でも、ラジオが始まってからは落ち着いて、
練習してきたとおりのトークができて
とても楽しめました。」
そのつぶやき通り「ゆっくり、元気のよい」トーク。
生放送でこれだけ話せたのですから、
まさに「自信」をもっていいですね。

後藤「本番前は全然緊張していなかったのに、
いざ始まると気づかないうちに
緊張していたみたいで、
とても早口になっていました。
途中からやっと慣れて、
いつも通りに話すことができました。
最初のトークで
少しグダってしまったのが、心残りです。」
いえいえ、大丈夫。
BGMはアップテンポの曲です。
・・・それに気が付いたら、落ち着きのある、
これまでで最高のトークになっていましたよ。
水戸守「ラジオ前の打ち合わせの時点で
既に緊張していて、
スタジオに入ったとき、うまくできるかとか、
失敗したらどうしようとか
たくさん考えていたんですが、
いざ始まったら、落ち着いたトークもできたし、
番組を楽しく進めることができました。」
水戸守さんは、番組の第一声担当だったため、
緊張感がより強かったでしょうね。
ですが本当によくやりました!

横路「本番ならではの緊張感が
とても楽しかったです。
いつも以上にスムーズに進み、
自分たちの企画した番組が形となり、
嬉しかったです。
元気いっぱい楽しくトークできました。」
はい、本当に楽しそうでした。
これはとても大事なことで、
だからこそリスナーの皆さんにも
元気や楽しさを感じてもらえますね。

渡辺「本番は少しドキドキしましたが、
始まるとなんだかテンションが上がってすごく楽しかったです。
自分たちの好きな曲なので落ち着いて
いつも通りのトークができたかと思います。
度胸がつきました!
貴重な体験をさせていただきました!」
はい、フリーで話すときもありましたが、
聞きやすく、そしてとても堂々と話していました。

近くで見ていて、頼もしく、
これだけの緊張感の中でも自分のことばで、
しかも笑顔でのトーク!
とてもとても立派でした。

また近いうちに本ブログで、
生放送に至るまでの裏話(!?)を
ご紹介していく予定です。
ゼミメンバー
後藤彩加 川崎花恋 小坂茉莉花
水戸守真理 渡辺小百合 横路久未
報告:平野美保
学生企画の、ラジオ番組生出演について、
本ブログでお伝えしてきました。
http://notredameningen.kyo2.jp/e468539.html
http://notredameningen.kyo2.jp/e465043.html
いよいよ本番当日の7月11日。
本番前に皆で集まって最終の打ち合わせをし、



そして本番の13:04を迎えました。
第1部の「ことばアンテナ」も
第2部の「あなたの青春 Music Travel」も、
それぞれの持ち味を十二分に発揮しての放送であったと思います。
放送を終えたばかりのメンバーに、
生放送出演の感想を聞いてみました。
小坂「始まる前はとても緊張していたけど、
ラジオが始まってみれば、
さっきまでのドキドキはどこかに消え、
話すのが楽しい!
というワクワクした気持ちになっていました。」
ドキドキからワクワク・・・
同じ緊張感でも、とても楽しい緊張感でしたね。

川崎「スタジオに入って、
ヘッドフォンをつけてから
緊張がピークになって、
少しでも落ち着くために、
メンバーで
「ゆっくり、元気よく、自信をもって!!」と
何回もつぶやきました。
でも、ラジオが始まってからは落ち着いて、
練習してきたとおりのトークができて
とても楽しめました。」
そのつぶやき通り「ゆっくり、元気のよい」トーク。
生放送でこれだけ話せたのですから、
まさに「自信」をもっていいですね。

後藤「本番前は全然緊張していなかったのに、
いざ始まると気づかないうちに
緊張していたみたいで、
とても早口になっていました。
途中からやっと慣れて、
いつも通りに話すことができました。
最初のトークで
少しグダってしまったのが、心残りです。」
いえいえ、大丈夫。
BGMはアップテンポの曲です。
・・・それに気が付いたら、落ち着きのある、
これまでで最高のトークになっていましたよ。
水戸守「ラジオ前の打ち合わせの時点で
既に緊張していて、
スタジオに入ったとき、うまくできるかとか、
失敗したらどうしようとか
たくさん考えていたんですが、
いざ始まったら、落ち着いたトークもできたし、
番組を楽しく進めることができました。」
水戸守さんは、番組の第一声担当だったため、
緊張感がより強かったでしょうね。
ですが本当によくやりました!

横路「本番ならではの緊張感が
とても楽しかったです。
いつも以上にスムーズに進み、
自分たちの企画した番組が形となり、
嬉しかったです。
元気いっぱい楽しくトークできました。」
はい、本当に楽しそうでした。
これはとても大事なことで、
だからこそリスナーの皆さんにも
元気や楽しさを感じてもらえますね。

渡辺「本番は少しドキドキしましたが、
始まるとなんだかテンションが上がってすごく楽しかったです。
自分たちの好きな曲なので落ち着いて
いつも通りのトークができたかと思います。
度胸がつきました!
貴重な体験をさせていただきました!」
はい、フリーで話すときもありましたが、
聞きやすく、そしてとても堂々と話していました。

近くで見ていて、頼もしく、
これだけの緊張感の中でも自分のことばで、
しかも笑顔でのトーク!
とてもとても立派でした。

また近いうちに本ブログで、
生放送に至るまでの裏話(!?)を
ご紹介していく予定です。
ゼミメンバー
後藤彩加 川崎花恋 小坂茉莉花
水戸守真理 渡辺小百合 横路久未
報告:平野美保
2015年07月10日
椅子のある大学
本学のキャンパスには
あちこちにふと座ることのできる、
ソファーや椅子があります。

戸外にも、こんなベンチを、
置いています。

周囲の風景を映し出す
ユージニア館のグラスドームの内側には、
小さい机と椅子が置かれています。

休み時間に話をしたり、
本を読んだりして、
ひとときを過ごすこともできます。


こういう場所があるのは、
少しゆったりとした時間を、
持ってほしいからです。
大学は授業を受けるだけの場所では、
ありません。
自分のしたいことを見つけるところです。
とはいえ、
教室では授業をしてうるわけですから、
自分の好きなことをするわけにも、
いきません。

勉強をするなら、
ぜひ図書館のラーニングコモンズを、
使ってほしいのですが、
ぼーっとしたり、
友人と何となく話す時間も大切だと思います。
そんな時間が自分を見つける、
機会になるでしょう。

そんなわけで、キャンパスのあちこちには、
少し憩うことのできる場所が、
あります。

報告:長沼光彦
あちこちにふと座ることのできる、
ソファーや椅子があります。

戸外にも、こんなベンチを、
置いています。

周囲の風景を映し出す
ユージニア館のグラスドームの内側には、
小さい机と椅子が置かれています。

休み時間に話をしたり、
本を読んだりして、
ひとときを過ごすこともできます。


こういう場所があるのは、
少しゆったりとした時間を、
持ってほしいからです。
大学は授業を受けるだけの場所では、
ありません。
自分のしたいことを見つけるところです。
とはいえ、
教室では授業をしてうるわけですから、
自分の好きなことをするわけにも、
いきません。

勉強をするなら、
ぜひ図書館のラーニングコモンズを、
使ってほしいのですが、
ぼーっとしたり、
友人と何となく話す時間も大切だと思います。
そんな時間が自分を見つける、
機会になるでしょう。

そんなわけで、キャンパスのあちこちには、
少し憩うことのできる場所が、
あります。

報告:長沼光彦
2015年07月09日
新キャンパス完成と催し物
以前、6月に新キャンパスが完成しました、
とお伝えしました。

そして、
7月22日(水)には完成式典が行われ、
正式にお祝いすることになります。

他にも、新しいキャンパスを、
ご覧いただく機会を用意しています。

まずは、オープンキャンパスです。
7月19日(日)、8月1日(土)、2日(日)、
8月23日(日)、9月13日(日)。

10月24日(土)、25日(日)は、
大学祭(ND祭)開催中に、
オープンキャンパスも行います。

また、公開講座も行います。
7月19日(日)に、オープンキャンパスと同時開催で、
「図書館を学びの場として使いこなす」。
10月18日(日)は、
「琳派400年を記念して『尾形光琳と小袖ファッション』」
を開催します。
こちらも、ぜひおいでください。

ただいま、京都市営地下鉄車両内に、
新オープンキャンパス完成と、
催し物のお知らせを掲示しています。
(乗ったことのない方には、
わかりにくいかと思いますが、
本学のある北山から京都方面の列車の場合、
一番前の車両、
運転席の裏に掲示しています。)

お目にかかった際には、
よろしくお願いいたします。

報告:長沼光彦
とお伝えしました。

そして、
7月22日(水)には完成式典が行われ、
正式にお祝いすることになります。

他にも、新しいキャンパスを、
ご覧いただく機会を用意しています。

まずは、オープンキャンパスです。
7月19日(日)、8月1日(土)、2日(日)、
8月23日(日)、9月13日(日)。

10月24日(土)、25日(日)は、
大学祭(ND祭)開催中に、
オープンキャンパスも行います。

また、公開講座も行います。
7月19日(日)に、オープンキャンパスと同時開催で、
「図書館を学びの場として使いこなす」。
10月18日(日)は、
「琳派400年を記念して『尾形光琳と小袖ファッション』」
を開催します。
こちらも、ぜひおいでください。

ただいま、京都市営地下鉄車両内に、
新オープンキャンパス完成と、
催し物のお知らせを掲示しています。
(乗ったことのない方には、
わかりにくいかと思いますが、
本学のある北山から京都方面の列車の場合、
一番前の車両、
運転席の裏に掲示しています。)

お目にかかった際には、
よろしくお願いいたします。

報告:長沼光彦
2015年07月08日
花のある大学 八
雨続きで、ソフィア館エントランスの薔薇も、
花びらを濡らしています。

実は、お花は、屋外だけでなく、
室内にも飾られています。

ソフィア館に入ると、右手に、
ローマ法王フランスシコ,
ノートルダム修道女会の創始者、
マザー・ゲルハルディンガーの肖像が飾られ、
その前に、白い百合が飾られています。

白百合は、聖母マリアの象徴(マドンナリリー)です。

入ると、ちょっとしたスペースがあり、
椅子の横には、以前ご紹介した、
紫陽花が飾られています。

ユージニア館も、お花が飾られています。
2階のお御堂には、マリア様の木造の近くに、
池坊華道同好会により花が活けられています。


4回エレベーターホールには、
華道部により花が活けられています。

大学の校舎の中にも、
少し歩くと、
潤いを見つけることができます。
報告:長沼光彦
花びらを濡らしています。

実は、お花は、屋外だけでなく、
室内にも飾られています。

ソフィア館に入ると、右手に、
ローマ法王フランスシコ,
ノートルダム修道女会の創始者、
マザー・ゲルハルディンガーの肖像が飾られ、
その前に、白い百合が飾られています。

白百合は、聖母マリアの象徴(マドンナリリー)です。

入ると、ちょっとしたスペースがあり、
椅子の横には、以前ご紹介した、
紫陽花が飾られています。

ユージニア館も、お花が飾られています。
2階のお御堂には、マリア様の木造の近くに、
池坊華道同好会により花が活けられています。


4回エレベーターホールには、
華道部により花が活けられています。

大学の校舎の中にも、
少し歩くと、
潤いを見つけることができます。
報告:長沼光彦
2015年07月07日
七夕の夜に勉強
本日7月7日は、七夕ですが、
京都はあいにくの雨模様です。
夜には晴れたので、
もう少し遅くなれば、
雲間から星が見えるかもしれませんが。

もっとも、京都は、
催事としては、旧暦で七夕をする場合が、
多いようです。
(清水寺の地主神社では、
本日7月7日に、七夕こけしお祓い、
という行事をしているようです。)
京の七夕という催事が、
8月1日から10日にかけて、
予定されています。
新暦では、梅雨にあたることが多いので、
星を見る七夕は、旧暦で行うのも、
良いかもしれません。
どちらもお祝いするのも良いでしょう。
夜7時頃、図書館をのぞいてみると、
七夕だからというわけではないのでしょうが、
ラーニングコモンズで、
学生さんたちが勉強していました。

聞くと、日本語教員の模擬授業をするために、
準備をしているのだそうです。
どのようなシチュエーションか理解してもらうために、
絵を描いたり、写真を準備したり、
視覚的な教材を作成しています。
本番さながらの、用意をしなければいけません。
グループで活動しているので、
話し合いも必要です。
いろいろと資料があって、
話し合いもでき、、パソコンも使用できる、
図書館のスペース、
ラーニングコモンズは、
準備に適しているようです。

こんなに夜遅くに勉強してるものなのか、
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
必要があれば、勉強するものでしょう。
近年の大学生は、
授業だけで授業をすます傾向があると、
報道されたこともあります。
一方で、
予習する必然、準備する必然があれば、
勉強する学生さんもいるわけです。
勉強できる機会づくり、環境づくりも必要かと思います。
グループワークを主体とした学習は、
相互に協力しながら、
能動的に取り組む場と機会が得られる方法です。
また、ラーニングコモンズのような場所が、
そのような学習をしやすくする環境を、
提供します。
(最近は、こういう能動的な学習を、
アクティブラーニングと呼んでいます。)
そんな学生さんの活動を見て、
頼もしい気持ちになり、
何してますか、と調子にのって、
話しかけ、話し込みすぎたと気づいて、
退散してきました。
邪魔してはいけませんね。

報告:長沼光彦
京都はあいにくの雨模様です。
夜には晴れたので、
もう少し遅くなれば、
雲間から星が見えるかもしれませんが。

もっとも、京都は、
催事としては、旧暦で七夕をする場合が、
多いようです。
(清水寺の地主神社では、
本日7月7日に、七夕こけしお祓い、
という行事をしているようです。)
京の七夕という催事が、
8月1日から10日にかけて、
予定されています。
新暦では、梅雨にあたることが多いので、
星を見る七夕は、旧暦で行うのも、
良いかもしれません。
どちらもお祝いするのも良いでしょう。
夜7時頃、図書館をのぞいてみると、
七夕だからというわけではないのでしょうが、
ラーニングコモンズで、
学生さんたちが勉強していました。

聞くと、日本語教員の模擬授業をするために、
準備をしているのだそうです。
どのようなシチュエーションか理解してもらうために、
絵を描いたり、写真を準備したり、
視覚的な教材を作成しています。
本番さながらの、用意をしなければいけません。
グループで活動しているので、
話し合いも必要です。
いろいろと資料があって、
話し合いもでき、、パソコンも使用できる、
図書館のスペース、
ラーニングコモンズは、
準備に適しているようです。

こんなに夜遅くに勉強してるものなのか、
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
必要があれば、勉強するものでしょう。
近年の大学生は、
授業だけで授業をすます傾向があると、
報道されたこともあります。
一方で、
予習する必然、準備する必然があれば、
勉強する学生さんもいるわけです。
勉強できる機会づくり、環境づくりも必要かと思います。
グループワークを主体とした学習は、
相互に協力しながら、
能動的に取り組む場と機会が得られる方法です。
また、ラーニングコモンズのような場所が、
そのような学習をしやすくする環境を、
提供します。
(最近は、こういう能動的な学習を、
アクティブラーニングと呼んでいます。)
そんな学生さんの活動を見て、
頼もしい気持ちになり、
何してますか、と調子にのって、
話しかけ、話し込みすぎたと気づいて、
退散してきました。
邪魔してはいけませんね。

報告:長沼光彦
2015年07月06日
LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学)でのOSC出展決定!
本学の人間文化学科の吉田智子研究室に窓口のある「LilyPad研究会」
が、8月に京都で実施される「オープンソースカンファレンス(OSC 8/7, 8/8)」に、
展示ブースを構えることが、正式に決まりました!
手芸やかわいい小物作りに、必要に応じてプログラミングを活用する
というのが、LilyPad研究会の考え方。8月の展示や発表に向けての
制作が本格的になっています。
2011年より吉田智子が、京都でのOSCというイベントの
実行委員長を務めている関係で、ノートルダムの学生が毎年、
運営に、展示に、司会にと活躍していることは、
このブログで広報しているとおりです。しかし、
「LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学)」
という名前の展示ブースを構えるのは、実は今年が初めてなのです。
(「ローカルスタッフ有志」の展示やセミナーは今年もやります。そして、
そちらにもノートルダムの学生は積極的に参加しています。)
なので、OSCの案内の「参加グループ」の中間あたりに、
大学名がリストアップされているのを見て、ウキウキ・ワクワク・ドキドキしています。
また、展示ブース一覧のところにも、
ブースの概要が、次のように紹介されています。
LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学) [教育/ハードウェア/プログラミング言語]
「かわいくマイコン制御」を合言葉に、LilyPad Arduinoを使ったテクノ手芸、
littleBitsを使った制作などを通してプログラミングを学びます。
以下の作品は、ある学生のテクノ手芸作品の制作中の写真。
紫色のマフラーのスナップをとめると、電気回路がつながって
LEDが派手に光りだすしくみになっているそうです。
学生自身が、そのしくみを考えて、マフラーとスナップを用意してきました。
マイコン(LilyPad Arduino)へのプログラム記述によって、
光らせ方は、変えることができます。
さらに、LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学)の展示ブースには、
UVレジンを使ったかわいいLED作品も展示し、その作り方も具体的に
紹介する予定で準備を進めています。(かわいいLED作りについてのブログ参照)
今回紹介した内容以外にもノートルダムの学生は、
littleBits とレゴを組み合わせた音で動き出す車の作品も展示するし、
アーテックのロボティストを使った「ロボット犬」も展示します。
当日をどうぞお楽しみに!
イベント(OSC京都、8/7, 8/8) の案内:http://www.ospn.jp/osc2015-kyoto/
LilyPad研究会の案内:http://lilypad.pen.jp/
報告:吉田智子
» 続きを読む
が、8月に京都で実施される「オープンソースカンファレンス(OSC 8/7, 8/8)」に、
展示ブースを構えることが、正式に決まりました!
手芸やかわいい小物作りに、必要に応じてプログラミングを活用する
というのが、LilyPad研究会の考え方。8月の展示や発表に向けての
制作が本格的になっています。
 |  |
| 左側は、自動演奏と手動演奏ができる「布ピアノ」です。音に対応したLEDが光ります。 |
2011年より吉田智子が、京都でのOSCというイベントの
実行委員長を務めている関係で、ノートルダムの学生が毎年、
運営に、展示に、司会にと活躍していることは、
このブログで広報しているとおりです。しかし、
「LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学)」
という名前の展示ブースを構えるのは、実は今年が初めてなのです。
(「ローカルスタッフ有志」の展示やセミナーは今年もやります。そして、
そちらにもノートルダムの学生は積極的に参加しています。)
なので、OSCの案内の「参加グループ」の中間あたりに、
大学名がリストアップされているのを見て、ウキウキ・ワクワク・ドキドキしています。
また、展示ブース一覧のところにも、
ブースの概要が、次のように紹介されています。
LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学) [教育/ハードウェア/プログラミング言語]
「かわいくマイコン制御」を合言葉に、LilyPad Arduinoを使ったテクノ手芸、
littleBitsを使った制作などを通してプログラミングを学びます。
以下の作品は、ある学生のテクノ手芸作品の制作中の写真。
紫色のマフラーのスナップをとめると、電気回路がつながって
LEDが派手に光りだすしくみになっているそうです。
学生自身が、そのしくみを考えて、マフラーとスナップを用意してきました。
マイコン(LilyPad Arduino)へのプログラム記述によって、
光らせ方は、変えることができます。
さらに、LilyPad研究会(京都ノートルダム女子大学)の展示ブースには、
UVレジンを使ったかわいいLED作品も展示し、その作り方も具体的に
紹介する予定で準備を進めています。(かわいいLED作りについてのブログ参照)
今回紹介した内容以外にもノートルダムの学生は、
littleBits とレゴを組み合わせた音で動き出す車の作品も展示するし、
アーテックのロボティストを使った「ロボット犬」も展示します。
当日をどうぞお楽しみに!
イベント(OSC京都、8/7, 8/8) の案内:http://www.ospn.jp/osc2015-kyoto/
LilyPad研究会の案内:http://lilypad.pen.jp/
報告:吉田智子
» 続きを読む
2015年07月05日
嵐山フィールドワーク その参
6月28日の嵐山フィールドワークは、
再び長辻通に入り、南へと下がります。
見えてきたのは、桂川に架かる渡月橋です。

現在の渡月橋は、
昭和9年(1934年)の建造物ですが、
はじめに桂川に橋を架けたのは、
これから訪れる法輪寺中興の祖、
道昌(どうしょう)が800年頃に行った、
桂川改修の時だとされます。
(虚空蔵法輪寺ホームページを、
ご参照ください。)

法輪寺は、もとは、和銅六年(713年)、
行基が創建し、その頃は、
葛井寺(かづのいでら)という名でした。
(写真は、渡月橋に近い、裏手側から、
法輪寺に向かう入り口です。)

『都名所図会』(安永9年 1780年)を見ると、
法輪寺と名が改められた逸話が紹介されています。

葛井寺で修行していた道昌が、
虚空蔵求聞持法(こくぞうぐもんじほう)の修行をしていると、
金星の光が衣の袖に当たりました。
そして袖に、虚空蔵菩薩の姿が浮かび上がったというのです。
以後、その袖を内に収めた虚空蔵菩薩を本尊とし、
法輪寺と名を改めたのです。
虚空蔵菩薩は、知恵をつかさどる菩薩であるため、後には、
関西のお子さんが、知恵を授かりにお参りする、
十三参りが行われるようになりました。
(学生の皆さんに聞くと、京都だけではなく、
大阪にお住まいの方もいらっしゃるそうです。)



法輪寺は小高いところにあるため、
桂川や渡月橋をはじめとした、
周辺を一望できます。
桜や紅葉の季節は、
華やかな景色を見渡せます。

寺の参道の途中に、電電宮という社があります。
本来は、道昌の伝説にある金星(明星)と、
雷の神様を祀る神社でしたが、
明治になって、電気、電波を守護する神となりました。

学生が持ってきたデジカメの電池が切れたというので、
祈ってみたらと促したところ、
不思議なことに、一時的に電池が回復し、
電電宮の写真を撮影することができました。

こんな出来事も、京都フィールドワークの、
面白さでしょうか。

法輪寺にお参りしたということで、
帰りは、十三参りのように、
振り返らずに渡月橋を渡っていくことにしました。
十三参りでは、お参りした後に、
渡月橋から振り返ると、
せっかくもらった知恵を置いてくると、
言われています。
(渡月橋を渡ると、真正面に法輪寺の塔が見えます。
振り返ると、まっすぐに知恵が戻っていきそうな、
気がするかもしれませんね。)

無事に渡ったあと、
乗り換えの都合があるということで、
バスに乗って帰ることにしました。
再び三条通りを東へと揺られていきました。
(写真はバス停から見た、
法輪寺の塔の覗く嵐山です。)
嵐山フィールドワーク、
これにて終幕でございます。
おつきあいいただき、ありがとうございます。
報告:長沼光彦
再び長辻通に入り、南へと下がります。
見えてきたのは、桂川に架かる渡月橋です。

現在の渡月橋は、
昭和9年(1934年)の建造物ですが、
はじめに桂川に橋を架けたのは、
これから訪れる法輪寺中興の祖、
道昌(どうしょう)が800年頃に行った、
桂川改修の時だとされます。
(虚空蔵法輪寺ホームページを、
ご参照ください。)

法輪寺は、もとは、和銅六年(713年)、
行基が創建し、その頃は、
葛井寺(かづのいでら)という名でした。
(写真は、渡月橋に近い、裏手側から、
法輪寺に向かう入り口です。)

『都名所図会』(安永9年 1780年)を見ると、
法輪寺と名が改められた逸話が紹介されています。

葛井寺で修行していた道昌が、
虚空蔵求聞持法(こくぞうぐもんじほう)の修行をしていると、
金星の光が衣の袖に当たりました。
そして袖に、虚空蔵菩薩の姿が浮かび上がったというのです。
以後、その袖を内に収めた虚空蔵菩薩を本尊とし、
法輪寺と名を改めたのです。
虚空蔵菩薩は、知恵をつかさどる菩薩であるため、後には、
関西のお子さんが、知恵を授かりにお参りする、
十三参りが行われるようになりました。
(学生の皆さんに聞くと、京都だけではなく、
大阪にお住まいの方もいらっしゃるそうです。)



法輪寺は小高いところにあるため、
桂川や渡月橋をはじめとした、
周辺を一望できます。
桜や紅葉の季節は、
華やかな景色を見渡せます。

寺の参道の途中に、電電宮という社があります。
本来は、道昌の伝説にある金星(明星)と、
雷の神様を祀る神社でしたが、
明治になって、電気、電波を守護する神となりました。

学生が持ってきたデジカメの電池が切れたというので、
祈ってみたらと促したところ、
不思議なことに、一時的に電池が回復し、
電電宮の写真を撮影することができました。

こんな出来事も、京都フィールドワークの、
面白さでしょうか。

法輪寺にお参りしたということで、
帰りは、十三参りのように、
振り返らずに渡月橋を渡っていくことにしました。
十三参りでは、お参りした後に、
渡月橋から振り返ると、
せっかくもらった知恵を置いてくると、
言われています。
(渡月橋を渡ると、真正面に法輪寺の塔が見えます。
振り返ると、まっすぐに知恵が戻っていきそうな、
気がするかもしれませんね。)

無事に渡ったあと、
乗り換えの都合があるということで、
バスに乗って帰ることにしました。
再び三条通りを東へと揺られていきました。
(写真はバス停から見た、
法輪寺の塔の覗く嵐山です。)
嵐山フィールドワーク、
これにて終幕でございます。
おつきあいいただき、ありがとうございます。
報告:長沼光彦
2015年07月04日
嵐山フィールドワーク その弐
さて嵐山フィールドワークですが、
嵐電嵐山駅を出て、
北に向かいます。
京都らしいイメージの、
天龍寺の北川、竹林の道を通るためです。

歩くのは、渡月橋から北へと続く、
お土産屋さんや飲食店の並ぶ長辻通りです。

お店を眺めて歩くのも、
なかなか楽しく、
湯葉ソフトの店や、煎餅屋さん、うなぎ屋さん、
などいろいろです。

今回は天龍寺には立ち寄りませんでしたが、
門の近くのお池をのぞくと、蓮の花が咲いていました。
泥の中から咲きながら清らかさを保つ蓮の花は、
仏の教えにかなうものとされています。


世界遺産に登録される天龍寺の開山は、
夢窓疎石(むそうそせき)です。
禅僧であり、中世日本の庭園設計者としても知られます。
京都のお庭を散策する際には、
知っておきたい名前です。
天龍寺の北、竹林の道を通っていくと、
野宮神社(ののみやじんじゃ)が見えてきます。


6月27日に訪れたので、
夏越の祓(なごしのはらえ)の、
茅の輪(ちのわ)が鳥居にしつらえてありました。
近年は縁結びで知られるようですが、
本来は、斎宮(さいぐう)が潔斎(けっさい)した地です。
表の由緒書にも記されているので、
お参りの前に由来を見ておきます。
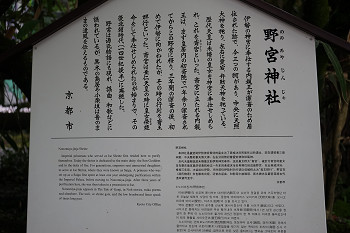
お参りの後は、
せっかくですから、本殿の脇の、
末社もお参りしましょう。
神社それぞれ、ゆかりのある神様が祀られています。


末社の前の苔庭も静謐な趣でした。

野宮神社を出ると、
トロッコ電車の軌道を少し覗いて、
元来た道を戻ります。

いよいよ、渡月橋、嵐山と、
いうところですが、また次回とさせていただきます。
下の写真は、学生がえらくお気に入りだった、
天龍寺横の通りにいらした、
お地蔵さんです。

報告:長沼光彦
嵐電嵐山駅を出て、
北に向かいます。
京都らしいイメージの、
天龍寺の北川、竹林の道を通るためです。

歩くのは、渡月橋から北へと続く、
お土産屋さんや飲食店の並ぶ長辻通りです。

お店を眺めて歩くのも、
なかなか楽しく、
湯葉ソフトの店や、煎餅屋さん、うなぎ屋さん、
などいろいろです。

今回は天龍寺には立ち寄りませんでしたが、
門の近くのお池をのぞくと、蓮の花が咲いていました。
泥の中から咲きながら清らかさを保つ蓮の花は、
仏の教えにかなうものとされています。


世界遺産に登録される天龍寺の開山は、
夢窓疎石(むそうそせき)です。
禅僧であり、中世日本の庭園設計者としても知られます。
京都のお庭を散策する際には、
知っておきたい名前です。
天龍寺の北、竹林の道を通っていくと、
野宮神社(ののみやじんじゃ)が見えてきます。


6月27日に訪れたので、
夏越の祓(なごしのはらえ)の、
茅の輪(ちのわ)が鳥居にしつらえてありました。
近年は縁結びで知られるようですが、
本来は、斎宮(さいぐう)が潔斎(けっさい)した地です。
表の由緒書にも記されているので、
お参りの前に由来を見ておきます。
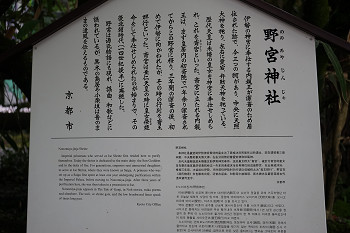
お参りの後は、
せっかくですから、本殿の脇の、
末社もお参りしましょう。
神社それぞれ、ゆかりのある神様が祀られています。


末社の前の苔庭も静謐な趣でした。

野宮神社を出ると、
トロッコ電車の軌道を少し覗いて、
元来た道を戻ります。

いよいよ、渡月橋、嵐山と、
いうところですが、また次回とさせていただきます。
下の写真は、学生がえらくお気に入りだった、
天龍寺横の通りにいらした、
お地蔵さんです。

報告:長沼光彦
2015年07月03日
嵐山フィールドワーク その壱
6月27日、嵐山へフィールドワークに行きました。
(下の写真は、嵐山の渡月橋です)

2年生ゼミは、京都をプレゼンしようという、
テーマで活動を進めています。
そこで、京都らしい場所に、
出かけてみることにしました。

出発するのは、四条大宮の、
嵐山電鉄の駅です。
(嵐電(らんでん)の駅のコカコーラの看板は、
赤ではなく黒でした。)

嵐山はJRでも、阪急でも行くことができます。
嵐山電鉄を利用したのは、
各駅停車で、京都から嵐山に至るまでの雰囲気を、
駅名から味わってもらおうと思ったからです。
(阪急は鈴虫寺、JRはトロッコ電車に乗り換え、
と目的によって、選ぶこともできます。)

蚕ノ社(かいこのやしろ)、太秦広隆寺(うづまさこうりゅうじ)、
帷子ノ辻(かたびらのつじ)、車折神社(くるまざきじんじゃ)、
鹿王院(ろくおういん)と、謂われのある名が続きます。

(上の写真は、嵐電の運転席です。)
嵐山電鉄は、明治43年(1910年)に開業、
行楽客の利用を期待していました。
開業当時に発行された『沿道名所案内』(嵐山電車軌道株式会社、1910・3)
を見ると、これら沿線の名所が紹介されています。
(『沿道名所案内』は、本学図書館で所蔵しています。)
現在の嵐電HPや、駅においてある「エリアマップ」にも、
沿線の名所が紹介されていますので、
ぜひご覧ください。

そんなわけで、駅名のいわれを話しているうちに、
嵐山に着きました。

嵐山駅は、京都風な味わいを演出するために、
錦織’(にしきおり)のような模様の柱が並んでいました。

まだ嵐山を歩いていませんが、今回はここまでにいたします。
嵐電だけでも、じゅうぶんに楽しめるというお話でした。

(駅構内タリーズコーヒーの前にも、錦の柱が立っています。)
今回のフィールドワークの目的地、嵐山は、
谷崎潤一郎『細雪』で、富裕層の三姉妹が、
花見に出かける場所として登場します。
このお話は、人間文化学科で発行した冊子、
『比較古都論』で紹介しています。
よろしければ、オープンキャンパスの際にでも、
お持ち帰りください。

もうひとつおまけの話です。
嵐電は、路面電車となる区域もあり、
(専門用語で併用軌道といいます。)
西大路三条という駅から、
三条通りを走ります。
以前ご紹介した三条通りの西側は、
太秦あたりまで続いているのです。
これも面白い話ですね。
報告:長沼光彦
(下の写真は、嵐山の渡月橋です)

2年生ゼミは、京都をプレゼンしようという、
テーマで活動を進めています。
そこで、京都らしい場所に、
出かけてみることにしました。

出発するのは、四条大宮の、
嵐山電鉄の駅です。
(嵐電(らんでん)の駅のコカコーラの看板は、
赤ではなく黒でした。)

嵐山はJRでも、阪急でも行くことができます。
嵐山電鉄を利用したのは、
各駅停車で、京都から嵐山に至るまでの雰囲気を、
駅名から味わってもらおうと思ったからです。
(阪急は鈴虫寺、JRはトロッコ電車に乗り換え、
と目的によって、選ぶこともできます。)

蚕ノ社(かいこのやしろ)、太秦広隆寺(うづまさこうりゅうじ)、
帷子ノ辻(かたびらのつじ)、車折神社(くるまざきじんじゃ)、
鹿王院(ろくおういん)と、謂われのある名が続きます。

(上の写真は、嵐電の運転席です。)
嵐山電鉄は、明治43年(1910年)に開業、
行楽客の利用を期待していました。
開業当時に発行された『沿道名所案内』(嵐山電車軌道株式会社、1910・3)
を見ると、これら沿線の名所が紹介されています。
(『沿道名所案内』は、本学図書館で所蔵しています。)
現在の嵐電HPや、駅においてある「エリアマップ」にも、
沿線の名所が紹介されていますので、
ぜひご覧ください。

そんなわけで、駅名のいわれを話しているうちに、
嵐山に着きました。

嵐山駅は、京都風な味わいを演出するために、
錦織’(にしきおり)のような模様の柱が並んでいました。

まだ嵐山を歩いていませんが、今回はここまでにいたします。
嵐電だけでも、じゅうぶんに楽しめるというお話でした。

(駅構内タリーズコーヒーの前にも、錦の柱が立っています。)
今回のフィールドワークの目的地、嵐山は、
谷崎潤一郎『細雪』で、富裕層の三姉妹が、
花見に出かける場所として登場します。
このお話は、人間文化学科で発行した冊子、
『比較古都論』で紹介しています。
よろしければ、オープンキャンパスの際にでも、
お持ち帰りください。

もうひとつおまけの話です。
嵐電は、路面電車となる区域もあり、
(専門用語で併用軌道といいます。)
西大路三条という駅から、
三条通りを走ります。
以前ご紹介した三条通りの西側は、
太秦あたりまで続いているのです。
これも面白い話ですね。
報告:長沼光彦
2015年07月02日
花のある大学 七
七月になりましたが、
まだ梅雨明けしないようです。


夏越しの祓があった六月三十日も、
夕方から雨が降りました。
夜には、上賀茂神社で夏越の祓式が行われ、
境内の、ならの小川に、
人形(ひとがた)が流される予定でしたが、
どうだったのでしょう。
この時期のお花といえば、
紫陽花(あじさい)ですが、
大学にも群生している場所があります。

大学の東側の通りに面したところに、
ふと見ると、紫陽花の花々が。
建物で言うと、テレジア館の裏側に、
あたります。
(キャンパスマップ)


最寄りの地下鉄、北山駅から、
帰ろうとする場合、
大学の西側に向かって歩くことになります。

そんなわけで、学生の皆さんで、
気づいていない形も多いかもしれません。

と思っていたら、
ちょうど帰る学生と顔を合わせ、
挨拶をされました。
知る人は知る、通学路の楽しみのようです。

報告:長沼光彦
まだ梅雨明けしないようです。


夏越しの祓があった六月三十日も、
夕方から雨が降りました。
夜には、上賀茂神社で夏越の祓式が行われ、
境内の、ならの小川に、
人形(ひとがた)が流される予定でしたが、
どうだったのでしょう。
この時期のお花といえば、
紫陽花(あじさい)ですが、
大学にも群生している場所があります。

大学の東側の通りに面したところに、
ふと見ると、紫陽花の花々が。
建物で言うと、テレジア館の裏側に、
あたります。
(キャンパスマップ)


最寄りの地下鉄、北山駅から、
帰ろうとする場合、
大学の西側に向かって歩くことになります。

そんなわけで、学生の皆さんで、
気づいていない形も多いかもしれません。

と思っていたら、
ちょうど帰る学生と顔を合わせ、
挨拶をされました。
知る人は知る、通学路の楽しみのようです。

報告:長沼光彦
2015年07月01日
おはなし会の練習を始めました
司書課程科目〈児童サービス論〉では、子どもたちへの図書館サービスのひとつであるお話会の方法と技術を学ぶため、授業の中で企画し、練習しています。読み聞かせ、ストーリーテリング、ブックトーク、読書へのアニマシオン、紙芝居、ペープサート、エプロンシアター、パネルシアターのうち、各自または各グループひとつを選んで、実際にクラスの中で実演します。
子どもの発達段階を考えながら、どの年齢層に、どんなお話を、あるいはどんなプログラムを、どの手法で提供するかを考えることは重要であり、また難しいものです。実演の際には、年齢と作品と手法を組み合わせた理由を説明してから始めます。また、実演は撮影し、授業後に各自自分の実演を見て、振り返り学習をします。
絵を描くことや語りの得意な学生もおり、また魅力的な工夫もいろいろと見られます。子どもたちを本の世界にいざなうさまざまな方法を身につけることも、司書課程における大切な学びのひとつです。

報告:岩崎 れい
子どもの発達段階を考えながら、どの年齢層に、どんなお話を、あるいはどんなプログラムを、どの手法で提供するかを考えることは重要であり、また難しいものです。実演の際には、年齢と作品と手法を組み合わせた理由を説明してから始めます。また、実演は撮影し、授業後に各自自分の実演を見て、振り返り学習をします。
絵を描くことや語りの得意な学生もおり、また魅力的な工夫もいろいろと見られます。子どもたちを本の世界にいざなうさまざまな方法を身につけることも、司書課程における大切な学びのひとつです。

報告:岩崎 れい