2017年08月31日
トランスフォーマー 最後の騎士王 京都で映画を観る
「トランスフォーマー最後の騎士王」

これも、まだ上映しているかと思いますが、
7月末に公開の、宇宙から来た、
金属生命(見た目はロボット)の話です。
今のところ、この系統の映画が好き、
という学生に出会っておりません。
また、情緒を重んじるような映画が好きな方は、
なぜ、ロボットやら怪物やらが、
暴れる話に、観客が行くのか、
わからないかもしれません。
ただ、歴史を遡れば、
神話や伝承の世界に、
怪物はつきものです。
人と怪物は、
いつも一緒に過ごしてきたのです。
(近代科学の世界では、
妄想とされたてきましたが。)
また、CGなど、視覚的刺激を求めるのも、
人間の嗜好のひとつです。
時代ごとの技術によって、
視覚的刺激は変化してきました。
その先端技術の中で、
尖鋭な刺激を人は求めてきました。

そんなわけで、
先端技術を駆使した映画で、
ロボットや怪物が暴れるものが、
多くの人に喜ばれるのです。
まあ、そんな理屈っぽいことを考えないで、
すげー、とか言って、
観ておけば良いかと思います。
ちなみに、今回のトランスフォーマーも、
車が追いかける場面は、
CGではなく、実写です。
CGと実写を適度に混ぜるのは、
現在の映画のリアリティを感じさせる、
技術のひとつです。
報告:長沼光彦
2017年08月30日
勉強と研究
教員は、研究をしてます、
などと学生に言うと、
勉強と研究は違うのですか、
と聞かれたりします。

私の携わる文学研究は、
調べる、という点で、
大きな違いは、ないでしょう。
違うとすれば、
勉強が、人がまとめた答を、
知ることだとすると、
研究は、自分で答を見つけること、
だということです。
同じ発見でも、人が見つけたものか、
自分で見つけたものか、
という違いがあるわけです。

すぐれた研究や思索にふれて、
学ぶだけでもじゅうぶんかもしれません。
ただ、自分で見つけようとすることで、
物事と積極的に関わることが、
できるでしょう。
せっかく大学に入ったわけですから、
自分で答を見つけてみることに、
挑戦するのも、
面白いと思います。
長沼光彦
タグ :研究
2017年08月29日
夏休みの教員は研究をしている
先生は、夏休みに何をしているんですか、
と学生から聞かれたりします。

バカンスに出かけるのだ、
と豪勢なことを、
言ってみたいところですが、
なかなか実現しません。
遊びや休み以外は、
研究をしています。
研究も、じっくりと考えるには、
まとまった時間が必要です。
私の研究している分野、
日本の近現代文学の研究では、
調べ始めると、
この資料も見たい、
と調べものが、
次々と増えていきます。
わあ、面倒だなあ、
と思われるかもしれませんが、
実は、調べ物が増えることは、
良いことです。
むしろ、「あたり」と、
言えます。

調べて、わかった、
終わり、というパターンは、
答はわかっても、
研究にはなりません。
次から次へと、
資料と資料の関係が、
見つかっていくと、
それだけ、視点が広がるわけです。
皆さんがお好みかどうかは、
わかりませんが、
そんなことを、夏休みにしています。
報告:長沼光彦
2017年08月28日
メアリと魔女の花 京都で映画を観る
ちょっと前の話ですが、
「メアリと魔女の花」を、
観ました。

学生も話題にしていましたが、
スタジオジブリにいたスタッフが、
つくったアニメ映画です。
宮崎駿監督が、
引退宣言をした後、
ジブリは、アニメ制作部門を、
一度解体することになりました。
(2014年の話ですね)
「メアリと魔女の花」は、
「思い出のマーニー」の監督を務めた、
米林宏昌が、監督をしています。
制作スタッフも、ジブリに関わった人が、
多くいるようです。
そんなわけで、観ていると、
スタジオジブリのアニメと言われても、
そう思ってしまうような出来映えです。

とはいえ、じっくり観ていると、
宮崎駿監督のアニメとは、
いろいろ違います。
実はジブリの時も、
宮崎駿が監督でないときには、
演出や、人物の動きが、
違いました。
もともと、監督によって、
できあがった表現は、
微妙に違ったのです。

それでも、何となく、
ジブリの作品は、
宮崎駿がつくっているような、
気がします。
実際、NHKのドキュメンタリーを観ていると、
監督が別に決まっていても、
宮崎駿は、口を出さずにいられないようです。
それが、作品の質をあげることもありますが、
若手の監督の試行錯誤を、
(場合によっては個性の表現を)
押さえてしまうことも、
あったようです。
そういう意味では、
宮崎駿を離れて、
アニメをつくる環境になったのは、
良いことでもあると思います。
優れた師匠を持つと、
弟子はなかなか大変なようです。
報告:長沼光彦
タグ :メアリと魔女の花
2017年08月27日
学生に勧められてアニメを観る
昨日と似た話ですが、
学生に勧められて、
アニメを観る場合もあります。
この前観たのは、
「ズートピア」です。

田舎から都会に出てきて、
夢をかなえるために、
がんばる、という、
シンプルな話ですが、
面白いですね。
街を、大きな列車が走っているのですが、
動物に合わせて、
ドアが複数ついています。
こんな列車つくるの面倒だなあ、
などと思いますが、
そこが、ズートピアの良いところ。
それぞれの特徴に合わせて、
多様性を活かす、
というところに、
ズートピアの、
街の考え方があります。

もちろん、これは制作者の、
考えですね。
多様性を実現するためには、
実は、手間をかけなければ、
ならないことが多いのです。
しかし、それぞれの違い、
特徴を知って、はじめて、
一緒に暮らす、豊かさが、
生まれてくるわけですね。
そんなことを、視覚的な表現で、
ユーモラスに描いているところが、
楽しいなと思いました。
実は、この多様性は、
メインストーリーにも、
関係してきます。
こんなふうに、思ったことを、
学生と話したりもします。
報告:長沼光彦
2017年08月26日
学生に勧められマンガを読む
私の日本近現代文学・日本文化ゼミでは、
ストーリーのあるものであれば、
小説でなくとも、マンガや映画でも、
研究の対象する場合もあります。

今回は、学生が卒論に取り上げるというので、
「ノラガミ」というマンガを、
私も読むことになりました。
日本の八百万の神の世界観をもとにして、
神の世界で、何やら、
権謀術数がめぐらされている、
という話になっているようです。
(まだ、連載中です。)
神様もきわめて人間的に描かれており、
その点では、日本の神話の世界に、
近いかと思います。
論じるならば、
日本神話の世界を調べたうえで、
どのように現代風にアレンジされているか、
考えてみると良いのではないか、
と思いました。

もっとも、マンガの面白さは、
神や人の、関係や情緒の描き方、
また、コミカルなエピソードにも、
あるかと思います。
そういう、マンガの構成の仕方を、
分析してみるのも、
よいかもしれません。
そういえば、アニメも見て下さい、
と言われていたのでした。
報告:長沼光彦
ストーリーのあるものであれば、
小説でなくとも、マンガや映画でも、
研究の対象する場合もあります。

今回は、学生が卒論に取り上げるというので、
「ノラガミ」というマンガを、
私も読むことになりました。
日本の八百万の神の世界観をもとにして、
神の世界で、何やら、
権謀術数がめぐらされている、
という話になっているようです。
(まだ、連載中です。)
神様もきわめて人間的に描かれており、
その点では、日本の神話の世界に、
近いかと思います。
論じるならば、
日本神話の世界を調べたうえで、
どのように現代風にアレンジされているか、
考えてみると良いのではないか、
と思いました。

もっとも、マンガの面白さは、
神や人の、関係や情緒の描き方、
また、コミカルなエピソードにも、
あるかと思います。
そういう、マンガの構成の仕方を、
分析してみるのも、
よいかもしれません。
そういえば、アニメも見て下さい、
と言われていたのでした。
報告:長沼光彦
2017年08月25日
夏休みだから図書館
夏休みですので、
図書館を占領してやるぞ、
などと思って出かけてみると、
学生の皆さんも、勉強をしていました。

大学の夏休みは、
9月中旬まで続くので、
まだ早いような気もしますが、
勉強している人もいました。
邪魔すると悪いので、
声はかけませんでしたが、
卒論などに取りくんでいる
のかもしれません。

大学は、もとより、
勉強(研究)するところですから、
むしろ自由な時間は、
図書館で調べもの、
ということもあるわけです。
報告:長沼光彦
2017年08月24日
オープンキャンパスは学生スタッフが活躍しています
本学のオープンキャンパスは、
学生スタッフが活躍しています。

まずは、受付で、
来場された方をご案内します。
全体説明会では、
学科の案内を、務めます。
担当するのは、放送同好会の、
学生です。

模擬授業や体験コーナーの、
サポートに入り、
相談コーナーでも、
教員と共にお相手いたします。
キャンパスツアーで、
大学をご案内します。
おしゃべりCafeでは、
授業や、サークルなど、
キャンパスライフについて、
自分の体験をもとに、
実感をお話しています。
9月10日には、
またオープンキャンパスがあります。
学生スタッフとお話いただき、
大学生活を知っていただければ、
と思います。
報告:長沼光彦
学生スタッフが活躍しています。

まずは、受付で、
来場された方をご案内します。
全体説明会では、
学科の案内を、務めます。
担当するのは、放送同好会の、
学生です。

模擬授業や体験コーナーの、
サポートに入り、
相談コーナーでも、
教員と共にお相手いたします。
キャンパスツアーで、
大学をご案内します。
おしゃべりCafeでは、
授業や、サークルなど、
キャンパスライフについて、
自分の体験をもとに、
実感をお話しています。
9月10日には、
またオープンキャンパスがあります。
学生スタッフとお話いただき、
大学生活を知っていただければ、
と思います。
報告:長沼光彦
2017年08月23日
オープンキャンパスで模擬授業をしました(8月20日)
こんにちは、人間文化学科の教員 吉田朋子 (担当科目は西洋美術史など)です。

8月20日に開催されたオープンキャンパスで
「西洋絵画解読 そのジェスチャーはいったいどういう意味?」というタイトルで
40分間の模擬授業をいたしました。
ヨーロッパ文化の源流は
ギリシア・ローマの古典古代、そしてキリスト教だといえますが
どちらも、「人間」が中心です。
そのため、美術作品でも、人間をいかに表現するか、が最重要となります。
そのおおきな手段のひとつが、身振り(ジェスチャー)。
ジェスチャーに注目すると、美術作品を理解するための様々なポイントが浮き彫りになります。

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン 《ブラック祭壇画》(中央パネル 41×68㎝)
1452~55年頃 ルーヴル美術館
こちらの作品のイエス・キリストの右手のポーズは
祝福を表します。 固定した約束事としての身振りの一例です。
(仏像の印相と似ていますね)
しかし、物語的な性格の強い作品では、より自然で、日常生活の延長にあるような身振りが必要になります。
それと同時に、鑑賞者の視線や感情を誘導することも必要です。

ジョット 《キリスト捕縛》
1304~1306年 スクロヴェーニ礼拝堂 (パドヴァ)
ユダの裏切りが、マントでキリストを包み込む身振りで雄弁に語られています。
右の紫色の衣の人物は、キリストを指さして捕らえろと指示していますが、
同時に、わたしたち鑑賞者の視線も誘導しています。
そのほかにも、様々な作品を見ながら、
ジェスチャーを通じて、
作者の意図や鑑賞する私たちの心の動きを、
考えてみました。
高校ではあまり触れることのない「美術史」ですが、
楽しい学問です。 ぜひ、大学で親しんでいただきたいと思います。
(吉田朋子)

8月20日に開催されたオープンキャンパスで
「西洋絵画解読 そのジェスチャーはいったいどういう意味?」というタイトルで
40分間の模擬授業をいたしました。
ヨーロッパ文化の源流は
ギリシア・ローマの古典古代、そしてキリスト教だといえますが
どちらも、「人間」が中心です。
そのため、美術作品でも、人間をいかに表現するか、が最重要となります。
そのおおきな手段のひとつが、身振り(ジェスチャー)。
ジェスチャーに注目すると、美術作品を理解するための様々なポイントが浮き彫りになります。

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン 《ブラック祭壇画》(中央パネル 41×68㎝)
1452~55年頃 ルーヴル美術館
こちらの作品のイエス・キリストの右手のポーズは
祝福を表します。 固定した約束事としての身振りの一例です。
(仏像の印相と似ていますね)
しかし、物語的な性格の強い作品では、より自然で、日常生活の延長にあるような身振りが必要になります。
それと同時に、鑑賞者の視線や感情を誘導することも必要です。

ジョット 《キリスト捕縛》
1304~1306年 スクロヴェーニ礼拝堂 (パドヴァ)
ユダの裏切りが、マントでキリストを包み込む身振りで雄弁に語られています。
右の紫色の衣の人物は、キリストを指さして捕らえろと指示していますが、
同時に、わたしたち鑑賞者の視線も誘導しています。
そのほかにも、様々な作品を見ながら、
ジェスチャーを通じて、
作者の意図や鑑賞する私たちの心の動きを、
考えてみました。
高校ではあまり触れることのない「美術史」ですが、
楽しい学問です。 ぜひ、大学で親しんでいただきたいと思います。
(吉田朋子)
タグ :西洋美術史
2017年08月22日
祇園祭に行ってきました ―3年次生「専門演習」クラス2
次に通りかかったのは、芦刈山です。「芦刈」とは、大和物語などに出てくる有名なお話で、夫婦愛、固く結ばれた夫婦の絆をモチーフにしています。

ご神体は、落ちぶれて葦を刈る物語の主人公、元・夫です。右手に鎌、左手に刈り取った葦を持っています。衣装の一つ(旧衣装の小袖)に、天正17年(1589年)に制作されたものがあり、祇園祭のご神体の衣装としては現存最古だそうで、重要文化財に指定されています。この祭りの歴史の古さがうかがえますね。

人形の御頭はさらに古く、天文6年(1537年)に作られたとのこと。現在はレプリカを用いているそうです。

写真は、巡行の際に山を飾る懸装品の一つ、見送り。年によって使用されるものが異なり、右側が山口華楊画伯の「鶴図」を原画として織られた綴織、左側が江戸時代後期の「唐子喜遊図」で、今年は右の「鶴図」の方を使用するそうです。

こちらは、豊臣秀吉の陣羽織模様をもとに平成に入って新調された胴懸の綴織です。おもしろい鳥獣の図柄ですね。
晴れの日を飾る一つひとつの用品に、古くから多くの人々が熱い思いを籠めてきたことがわかります。
(報告者:堀勝博)
2017年08月21日
8月20日はオープンキャンパスでした
昨日、8月20日は、オープンキャンパスでした。
多くのご来場、ありがとうございます。

人間文化学科では、
吉田朋子先生が、
「絵画の中のジェスチャー」のテーマで、
模擬授業をしました。

絵画の中の、様々なポーズや仕草には、
どのような意味があるのか、
作品を紹介しながら、説明しました。
体験コーナーは、
鎌田先生による、
「簡単ムービー制作」と、
中里郁子先生による、
「聖句入りカードづくり」です。

ムービー制作は、
2年次ゼミ発展演習などで、
企画力、表現力を身につけるために、
採り入れています。

聖句入りカードづくりは、
聖書の言葉を自分で選び、
その言葉と水彩の絵を、
書き入れたカードを、
作るものです。

聖書に親しんでもらうために、
普段から行っている、
カトリック大学ならではの、
活動です。
今回は、来場した方が制作した、
カードをひとつ紹介しましょう。

絵は狼の求愛行動だそうです。
選んだ言葉は、
「愛は忍耐強い。
愛は情け深い。」
(コリント書13章4節)
です。
絵筆のタッチがすてきな作品です。
来場した方それぞれの、
個性が表れた作品が、
できました。
9月10日、日曜日に、
またオープンキャンパスがあります。
よろしければおいでください。
長沼光彦
多くのご来場、ありがとうございます。

人間文化学科では、
吉田朋子先生が、
「絵画の中のジェスチャー」のテーマで、
模擬授業をしました。

絵画の中の、様々なポーズや仕草には、
どのような意味があるのか、
作品を紹介しながら、説明しました。
体験コーナーは、
鎌田先生による、
「簡単ムービー制作」と、
中里郁子先生による、
「聖句入りカードづくり」です。

ムービー制作は、
2年次ゼミ発展演習などで、
企画力、表現力を身につけるために、
採り入れています。

聖句入りカードづくりは、
聖書の言葉を自分で選び、
その言葉と水彩の絵を、
書き入れたカードを、
作るものです。

聖書に親しんでもらうために、
普段から行っている、
カトリック大学ならではの、
活動です。
今回は、来場した方が制作した、
カードをひとつ紹介しましょう。

絵は狼の求愛行動だそうです。
選んだ言葉は、
「愛は忍耐強い。
愛は情け深い。」
(コリント書13章4節)
です。
絵筆のタッチがすてきな作品です。
来場した方それぞれの、
個性が表れた作品が、
できました。
9月10日、日曜日に、
またオープンキャンパスがあります。
よろしければおいでください。
長沼光彦
2017年08月20日
祇園祭に行ってきました ―3年次生「専門演習」クラス
大学は夏季休暇に入りましたが、7月にゼミで祇園祭見学に行ったときの記事を何回かに分けて報告します。
3年次生必修科目「専門演習」(ゼミ)の「日本語と古典」クラスでは、日本の古典文学や古い文化に興味を持つ学生が集まっています。
京都を代表する夏祭、祇園祭は、古典文学に深い関わりがありますので、毎年授業の一環として学生を見学に連れ出します。芦刈山、黒主山、木賊山、船鉾、鶏鉾、伯牙山、孟宗山など、古文漢文に取材した山や鉾が数多くあるのです。

今年のゼミ生は、とりわけ古典文学に強い興味をもつ学生が多いので、事前にそれらの山や鉾の由来となった古典文学原文をみっちり学習しました。
とは言っても、33基すべてを網羅することは難しいので、いくつかの山・鉾に焦点を絞りました。香港出身、中国出身の二人の留学生には、漢文学由来の山鉾を担当してもらいました。
見学したのは、お昼に行われる山鉾巡行ではなく、夕刻、駒形提燈に灯が点り、お祭ムードが溢れる宵山でした。まず目に入ったのは油天神山。

さっそく「ちまきどうどすかー」の掛け声でおみやげを売る少女たちのコーラスがわれわれを出迎えてくれました。
留学生たちも、初めて見るこのかわいい光景に目を細くしていました。 〈続〉
(報告者:堀勝博)
2017年08月19日
明日20日のオープンキャンパスへどうぞ
明日、20日、日曜日は、
オープンキャンパスです。
どうぞ、おいでください。

受験生の皆さんにとっては、
志望校決定前の、大切な時期だと思います。
高校1、2年生の皆さんは、
大学がどのような学びをしているか、
知る機会でしょう。
はじめての方は、本学の特徴ある学びを、
知ってください。
フレンドリーな学習環境で、
学んだことを社会で活かすことができるように、
授業やキャンパスライフの中で、
行動できる機会を多く設けています。
以前にいらした方は、
本学のカラーを再確認してください。
互いに尊重しながら、
協力して学ぶ学風を目指しています。
模擬授業で、実際にどのようなことを、
勉強するのか、
確かめてみてください。

人間文化学科では、
自分の興味がどこにあるのか発見し、
それを具体的な形にしていくことを、
目指しています。
文学、美術、音楽、言語、思想、宗教、
など、文化の多様な側面を学ぶことができる、
授業を用意しています。
皆さんの興味に合う分野が、
きっとあると思います。
学生スタッフと、教員でお待ちしております。
お気軽に、ご相談ください。
報告:長沼光彦
オープンキャンパスです。
どうぞ、おいでください。

受験生の皆さんにとっては、
志望校決定前の、大切な時期だと思います。
高校1、2年生の皆さんは、
大学がどのような学びをしているか、
知る機会でしょう。
はじめての方は、本学の特徴ある学びを、
知ってください。
フレンドリーな学習環境で、
学んだことを社会で活かすことができるように、
授業やキャンパスライフの中で、
行動できる機会を多く設けています。
以前にいらした方は、
本学のカラーを再確認してください。
互いに尊重しながら、
協力して学ぶ学風を目指しています。
模擬授業で、実際にどのようなことを、
勉強するのか、
確かめてみてください。

人間文化学科では、
自分の興味がどこにあるのか発見し、
それを具体的な形にしていくことを、
目指しています。
文学、美術、音楽、言語、思想、宗教、
など、文化の多様な側面を学ぶことができる、
授業を用意しています。
皆さんの興味に合う分野が、
きっとあると思います。
学生スタッフと、教員でお待ちしております。
お気軽に、ご相談ください。
報告:長沼光彦
タグ :オープンキャンパス
2017年08月18日
卒業生が話してくれたこと 8月5日オープンキャンパス
8月5日オープンキャンパスには、
大学案内などでモデルをしてもらっている、
卒業生に話をしてもらいました。

4年生の就活のときには、
求人情報が出ていないところに、
積極的に自分を売り込み、
就職することができたという、
行動力を発揮した人です。
ところが、大学に入るまでは、
自分から、人前に出て、
積極的に行動するようなタイプでは、
なかった、と言います。
変わったのは、
大学生活を送る中で、
いくつかきっかけがあったのだそうです。
そのひとつが、人間文化学科の、
話しことば教育、だとのことです。

他の大学にない特徴に、
興味を持ち、3年生では、
平野美保先生の、
話し言葉ゼミに入りました。
そこで、人前で司会をしたり、
ラジオ出演したりすることで、
自信がついたのだそうです。
また、当日も行った、
ラジオ番組風の、
学生による学科紹介は、
在学当時のゼミで、
ゼミ学生の発案により、
始まったものだ、とのことです。
ゼミの中でも、
積極的に企画・発案する、
雰囲気があった、ということですね。
こんなふうに、
いろいろな場所で活動するきっかけを得て、
互いに刺激しあう環境があったおかげで、
自ら進んで行動するようになれた、
と話してくれました。

人間文化学科では、
自分の発案を活かしたり、
進んで行動し、
コミュニケーションを行うことができる、
機会を、授業の中で用意しています。
そういう機会を活かしてもらえたら、
何よりだと思います。
報告:長沼光彦
大学案内などでモデルをしてもらっている、
卒業生に話をしてもらいました。

4年生の就活のときには、
求人情報が出ていないところに、
積極的に自分を売り込み、
就職することができたという、
行動力を発揮した人です。
ところが、大学に入るまでは、
自分から、人前に出て、
積極的に行動するようなタイプでは、
なかった、と言います。
変わったのは、
大学生活を送る中で、
いくつかきっかけがあったのだそうです。
そのひとつが、人間文化学科の、
話しことば教育、だとのことです。

他の大学にない特徴に、
興味を持ち、3年生では、
平野美保先生の、
話し言葉ゼミに入りました。
そこで、人前で司会をしたり、
ラジオ出演したりすることで、
自信がついたのだそうです。
また、当日も行った、
ラジオ番組風の、
学生による学科紹介は、
在学当時のゼミで、
ゼミ学生の発案により、
始まったものだ、とのことです。
ゼミの中でも、
積極的に企画・発案する、
雰囲気があった、ということですね。
こんなふうに、
いろいろな場所で活動するきっかけを得て、
互いに刺激しあう環境があったおかげで、
自ら進んで行動するようになれた、
と話してくれました。

人間文化学科では、
自分の発案を活かしたり、
進んで行動し、
コミュニケーションを行うことができる、
機会を、授業の中で用意しています。
そういう機会を活かしてもらえたら、
何よりだと思います。
報告:長沼光彦
Posted by 京都ノートルダム女子大学 国際日本文化学科(人間文化学科)
at 15:00
│Comments(0)
│話しことば教育│卒業生│キャリア教育・就活・インターンシップ│アクティブラーニング
2017年08月17日
愛宕山に登る 学生のフィールドワーク
8月1日2時の日付で、愛宕山に登った、
という知らせ(LINE)をもらいました。

何しに行ったの、と聞くと、
火の用心のお札をもらいに行った、
とのことでした。
なるほど、愛宕山の愛宕神社は、
火伏せ(ひぶせ)の神として知られます。
7月31日夕刻から、8月1日早朝の参拝は、
千日詣(せんにちまいり)と呼ばれ、
千日分の防火の御利益があるとされます。
飲食店でバイトをする知り合いと、
その店のご主人と一緒に登ったのだそうです。
きっと御利益があることと思います。
願いを叶えるためには、
苦労をする必要があるわけですね。
(今回は、山登りです。)

防火のように、身近な願いをかける行事は、
京都に住まう人とおつきあいがあることで、
知ったのでしょう。
有名な祭に行くのも良いのですが、
京都の人とお知り合いになり、
身近な行事を教えてもらうのも、
京都フィールドワークですね。
(勉強していくよりも、
生きたフィールドワークと、
言えるかもしれません。)

写真:アリス
報告:長沼光彦
という知らせ(LINE)をもらいました。

何しに行ったの、と聞くと、
火の用心のお札をもらいに行った、
とのことでした。
なるほど、愛宕山の愛宕神社は、
火伏せ(ひぶせ)の神として知られます。
7月31日夕刻から、8月1日早朝の参拝は、
千日詣(せんにちまいり)と呼ばれ、
千日分の防火の御利益があるとされます。
飲食店でバイトをする知り合いと、
その店のご主人と一緒に登ったのだそうです。
きっと御利益があることと思います。
願いを叶えるためには、
苦労をする必要があるわけですね。
(今回は、山登りです。)

防火のように、身近な願いをかける行事は、
京都に住まう人とおつきあいがあることで、
知ったのでしょう。
有名な祭に行くのも良いのですが、
京都の人とお知り合いになり、
身近な行事を教えてもらうのも、
京都フィールドワークですね。
(勉強していくよりも、
生きたフィールドワークと、
言えるかもしれません。)

写真:アリス
報告:長沼光彦
2017年08月16日
8月20日はオープンキャンパスです
8月20日、日曜日は、
オープンキャンパスです。

夏休みが終わる前に、
よろしければ、本学においでください。
人間文化学科の模擬授業は、
吉田朋子先生による、
「絵画の見方」です。

絵画は、どのようなポイントに注目して、
鑑賞したら味わえるか、
普段の講義をふまえて、
ご紹介します。
体験コーナーは、
中里郁子先生による「聖句入りカードづくり」と、
鎌田均先生による「簡単ムービー制作」です。

「聖句入りカードづくり」は、
聖書の中から選んだ言葉を、
絵のついたカードとしてしあげるものです。
普段も大学の中で、
聖書に親しむ活動として、
行っているものです。
カトリック大学らしい活動を、
体験してみてください。
「簡単ムービー制作」は、
2年次ゼミ、発展演習などで行っている、
プロジェクト形授業の体験です。

発展演習では、
自分でインターネット番組を企画し、
制作しています。
表現力を身につけるきっかけとして、
体験してみてはいかがでしょうか。
学生スタッフとともに、
お待ちしております。
ぜひ足を運んでください。
報告:長沼光彦
タグ :オープンキャンパス
2017年08月15日
夏越の祓の思い出 続 学生のフィールドワーク
昨日の続き、上賀茂神社の、
夏越の祓(なごしのはらえ)の儀式を紹介します。

学生が写真を送ってくれたものです。

6月30日、上賀茂神社、
夏越の祓、夕刻の儀式は、
ならの小川にかかる橋殿(はしのどの)で、
行われます。
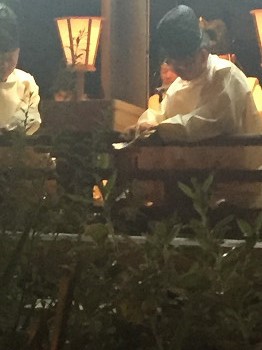
上賀茂神社の宮司さんが、
祓の詞(はらえのことば)を唱え、
氏子さんら託された人形(ひとがた)を、
ならの小川に流し、祓を行います。

人形は、氏子さんらが、
自分の体についた穢れ(けがれ)を、
うつしたものです。
人形が祓われることで、
当人の穢れが清くなることを、
祈るのです。
人形は、火で清められることもあるのですが、
水で清められるところに、
上賀茂神社の儀式の特徴があります。

写真:アリス
報告:長沼光彦
夏越の祓(なごしのはらえ)の儀式を紹介します。

学生が写真を送ってくれたものです。

6月30日、上賀茂神社、
夏越の祓、夕刻の儀式は、
ならの小川にかかる橋殿(はしのどの)で、
行われます。
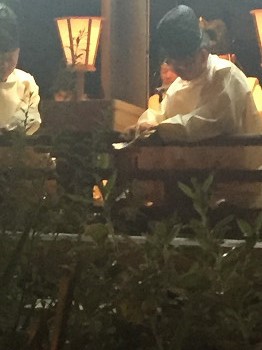
上賀茂神社の宮司さんが、
祓の詞(はらえのことば)を唱え、
氏子さんら託された人形(ひとがた)を、
ならの小川に流し、祓を行います。

人形は、氏子さんらが、
自分の体についた穢れ(けがれ)を、
うつしたものです。
人形が祓われることで、
当人の穢れが清くなることを、
祈るのです。
人形は、火で清められることもあるのですが、
水で清められるところに、
上賀茂神社の儀式の特徴があります。

写真:アリス
報告:長沼光彦
2017年08月14日
夏越の祓の思い出 学生のフィールドワーク
以前の話ですが、
上賀茂神社の夏越の祓(なごしのはらえ)を、
ご紹介します。

学生が写真を送ってくれました。
夏越の祓は、6月30日、大学の近くでは、
上賀茂神社、上御霊神社、吉田神社などで、
行われます。
上賀茂神社では、午前中と、
夕刻からと、2度行事が行われます。

この写真は、夕刻の儀式が行われる前に、
茅の輪くぐり(ちのわくぐり)をしている、
参拝者の皆さんの様子です。
上賀茂神社では、午前10時から、
宮司さんたちが、茅の輪くぐりの、
儀式を行います。
はじめに、神官さんたちが、
茅の輪をくぐり、お祓いをします。
その後、場所を、境内を流れる、
ならの小川にかけられた、
橋殿(はしどの)にうつします。
そこで、紙でつくられた御饌(みけ)を捧げ、
祓えの儀式を行います。
紙の御饌(みけ)は、儀式のあとに、
ならの小川に流されます。
その後、参拝者の皆さんが、
茅の輪をくぐることになります。
上賀茂神社独特の儀式ですので、
一度、参拝されてはいかがでしょうか。
写真:アリス
報告;長沼光彦
上賀茂神社の夏越の祓(なごしのはらえ)を、
ご紹介します。

学生が写真を送ってくれました。
夏越の祓は、6月30日、大学の近くでは、
上賀茂神社、上御霊神社、吉田神社などで、
行われます。
上賀茂神社では、午前中と、
夕刻からと、2度行事が行われます。

この写真は、夕刻の儀式が行われる前に、
茅の輪くぐり(ちのわくぐり)をしている、
参拝者の皆さんの様子です。
上賀茂神社では、午前10時から、
宮司さんたちが、茅の輪くぐりの、
儀式を行います。
はじめに、神官さんたちが、
茅の輪をくぐり、お祓いをします。
その後、場所を、境内を流れる、
ならの小川にかけられた、
橋殿(はしどの)にうつします。
そこで、紙でつくられた御饌(みけ)を捧げ、
祓えの儀式を行います。
紙の御饌(みけ)は、儀式のあとに、
ならの小川に流されます。
その後、参拝者の皆さんが、
茅の輪をくぐることになります。
上賀茂神社独特の儀式ですので、
一度、参拝されてはいかがでしょうか。
写真:アリス
報告;長沼光彦
2017年08月13日
授業紹介(情報・メディアの文化とリテラシー)
3年前から「情報・メディアの文化とリテラシー」という授業を隔年で開講しています。図書館などの、情報を扱ってきた分野では、情報を使いこなす能力を「情報リテラシー」と呼び、我々がそれを身につけることが重要だとしてきました。また、メディア学、メディア教育の分野でも、テレビ、新聞などのメディアの性質を理解できる能力である「メディアリテラシー」があり、デジタル機器を使いこなす能力など、様々な「リテラシー」が提唱されてきました。近年はインターネットなどによって、様々な情報源、メディアが融合しつつある中で、そういった情報、メディアを使いこなすことができる横断的な能力が必要とされつつあります。

この授業では、そのような能力について学びながら、情報、メディアと人との関わりについて考えます。SNSなどの情報にはどのような性質があり、それをどう使えばよいのか、どのようなことに気をつければよいのか、といった身近な問題から、情報を自分から発信すること、そこにおける法律、倫理などの理解など、情報、メディアに関する諸事情について学ぶ授業です。(なお、この記事にある画像は著作権フリーのものです。) (鎌田)

この授業では、そのような能力について学びながら、情報、メディアと人との関わりについて考えます。SNSなどの情報にはどのような性質があり、それをどう使えばよいのか、どのようなことに気をつければよいのか、といった身近な問題から、情報を自分から発信すること、そこにおける法律、倫理などの理解など、情報、メディアに関する諸事情について学ぶ授業です。(なお、この記事にある画像は著作権フリーのものです。) (鎌田)
タグ :メディアリテラシー
2017年08月12日
祇園祭の思い出 学生のフィールドワーク
先月の話ですが、学生が、
祇園祭に出かけた写真を、
送ってくれたので、紹介します。

四条通、烏丸交差点の、
長刀鉾ですね。

一緒に、もう一枚送ってくれました。
ウェスティン都ホテルから観た、
平安神宮だそうです。

向こうに、赤い鳥居が見えるでしょうか。
ウエスティン都ホテルは、
東山にあり、京都を一望できます。
京都にお住まいでない方は、
あまりご存じないかもしれませんが、
東山地域には、京都を一望できる場所が、
いくつかあります。
山で修行した、修験道の人や、
天狗になった気持ちで、
京都をみわたすことができるので、
おすすめです。
(そんな気持ちにならなくても、
良いのですが。)
(写真を送ってくれた学生に聞くのを、
忘れたのですが、
この写真は、同じ日に撮ったのかもしれません。)
(この学生は、行動的で、
1日で、何キロも移動することは、
よくあるようです。)
写真:アリス
報告:長沼光彦
祇園祭に出かけた写真を、
送ってくれたので、紹介します。

四条通、烏丸交差点の、
長刀鉾ですね。

一緒に、もう一枚送ってくれました。
ウェスティン都ホテルから観た、
平安神宮だそうです。

向こうに、赤い鳥居が見えるでしょうか。
ウエスティン都ホテルは、
東山にあり、京都を一望できます。
京都にお住まいでない方は、
あまりご存じないかもしれませんが、
東山地域には、京都を一望できる場所が、
いくつかあります。
山で修行した、修験道の人や、
天狗になった気持ちで、
京都をみわたすことができるので、
おすすめです。
(そんな気持ちにならなくても、
良いのですが。)
(写真を送ってくれた学生に聞くのを、
忘れたのですが、
この写真は、同じ日に撮ったのかもしれません。)
(この学生は、行動的で、
1日で、何キロも移動することは、
よくあるようです。)
写真:アリス
報告:長沼光彦



