2013年06月24日
教員紹介 鎌田 均
4月より本学人間文化学科に着任した鎌田です。私の専門分野は図書館情報学という、図書館と情報に関する様々な領域を取り扱う、総合分野です。アメリカでの図書館司書としての経験から、図書館の実務に関する分野に焦点をおいてきましたが、近年は、図書館を介する、介しないにかかわらず、情報と、情報を発信、利用する人とのつながり方、情報からなにを読み取って知識へと繋げていくか、という過程と、それをどのように教育に役立てるかに深く関心を持っています。大学の教員という、学生と直接関われる立場、また、京都ノートルダム女子大の少人数制の環境を活かして、社会のさまざまな場面で、情報を深く理解し、利用することをめぐる諸問題を一緒に考えていきたいと思います。
今学期担当している科目のひとつ、「図書館情報資源特論」では、授業での課題として、受講生に、京都に関するテーマを自由に設定し、それについての調べ方のガイドである、「パスファインダー」というものを作ってもらいました。京野菜についての情報の調べ方、西陣織などさまざまなテーマについてのパスファインダーができあがりました。このような、実際になにかを調べ、つくりあげる、といった内容の授業を今後も行っていくつもりです。
報告 鎌田 均
今学期担当している科目のひとつ、「図書館情報資源特論」では、授業での課題として、受講生に、京都に関するテーマを自由に設定し、それについての調べ方のガイドである、「パスファインダー」というものを作ってもらいました。京野菜についての情報の調べ方、西陣織などさまざまなテーマについてのパスファインダーができあがりました。このような、実際になにかを調べ、つくりあげる、といった内容の授業を今後も行っていくつもりです。
報告 鎌田 均
2013年06月23日
情報処理士、Webデザイナーの卵たちへの特別講義
人間文化学部には、「情報処理士」と「Webデザイン実務士」の
資格取得を目指して、学んでいる学生がいます。

それぞれの資格の授業に、今年も、データ変換研究所の社長の
畑中豊司氏と、この会社でマーケティングを担当されている、
本大学の卒業生の片桐さんが、特別講師として来てくださいました。
畑中氏が特別講師として、本大学に来て下さるのは
今年で4度目。
我々が大学を卒業した直後という、非常に昔からの仕事仲間で、
最近は1年に一度の、しかもいつも同じ時期(初夏)なので、
「まるで七夕の織姫と彦星の再会みたいやねぇ~」
などと言いながら、来てもらっています。

まず、1時間目の情報処理士の資格の取得者が主に学んでいる
「情報科学応用」の授業では、社長の畑中氏が、
情報通信ネットワークと通信技術の発達で可能になった
「M2M(Machine to Machine)」のシステムについて、
データ変換研究所の商品である「Derimo」のデモや、
利用例を挙げながら、説明されました。
http://www.derimo.net/
Derimo (データ変換研究所のリモートコントロールフレームワーク・ソフトウェア)
Derimoシリーズには、教育用パッケージもあり、「Derimo for Education」という
名称で、教育機関に導入されているそうです。
私も導入を検討してみようと思います。

次の2時間目の「ウェブデザインI」という授業は、ウェブデザイン実務士の資格取得者
には、必修となる科目です。
畑中氏は、自社のウェブページを例に挙げて、広告戦略としての
「ブランディング戦略」について、説明されました。ちなみに、
ブランディングというのは、ブランドに対する共感や信頼などを
高めていく戦略のひとつで、定着していないブランドを育て上げる
意味もあるようです。
この考え方は、企業のWeb制作のためには、知っておくべき概念で、
ウェブデザイナーの卵が含まれる受講生は、熱心に耳を傾けていました。

次に、卒業生の片桐さんから、各社のウェブページを例にとって、
その会社の「ブランディング戦略」の分析結果が紹介されました。
「空気のにおい消しの2つの商品ブランド」の比較や、
「インスタントの2つのレトルトパックメーカ」のWebサイトの比較など、
普段は何気なくTVコマーシャルなどで見ているブランドイメージ
について、鋭く指摘してくださいました。

また、畑中氏は、学生からのリクエストのあった、
「食品ブランド、コーヒーチェーン、
デパート、衣料品メーカ、コンビ二」
などのそれぞれの企業のブランディング戦略についても臨機応変に
コメントされました。
突然、学生が口にしたブランド名について、ご存じの知識を
披露される畑中氏の雑学ぶり(雑学ではなく知識と呼ぶべきかも)
に、学生も私も感心しました。

お忙しい中、本当にありがとうございました。
来年も、来ていただけることを希望していますので、どうぞよろしくお願いします。
報告 吉田智子
資格取得を目指して、学んでいる学生がいます。

それぞれの資格の授業に、今年も、データ変換研究所の社長の
畑中豊司氏と、この会社でマーケティングを担当されている、
本大学の卒業生の片桐さんが、特別講師として来てくださいました。
畑中氏が特別講師として、本大学に来て下さるのは
今年で4度目。
我々が大学を卒業した直後という、非常に昔からの仕事仲間で、
最近は1年に一度の、しかもいつも同じ時期(初夏)なので、
「まるで七夕の織姫と彦星の再会みたいやねぇ~」
などと言いながら、来てもらっています。

まず、1時間目の情報処理士の資格の取得者が主に学んでいる
「情報科学応用」の授業では、社長の畑中氏が、
情報通信ネットワークと通信技術の発達で可能になった
「M2M(Machine to Machine)」のシステムについて、
データ変換研究所の商品である「Derimo」のデモや、
利用例を挙げながら、説明されました。
http://www.derimo.net/
Derimo (データ変換研究所のリモートコントロールフレームワーク・ソフトウェア)
Derimoシリーズには、教育用パッケージもあり、「Derimo for Education」という
名称で、教育機関に導入されているそうです。
私も導入を検討してみようと思います。

次の2時間目の「ウェブデザインI」という授業は、ウェブデザイン実務士の資格取得者
には、必修となる科目です。
畑中氏は、自社のウェブページを例に挙げて、広告戦略としての
「ブランディング戦略」について、説明されました。ちなみに、
ブランディングというのは、ブランドに対する共感や信頼などを
高めていく戦略のひとつで、定着していないブランドを育て上げる
意味もあるようです。
この考え方は、企業のWeb制作のためには、知っておくべき概念で、
ウェブデザイナーの卵が含まれる受講生は、熱心に耳を傾けていました。

次に、卒業生の片桐さんから、各社のウェブページを例にとって、
その会社の「ブランディング戦略」の分析結果が紹介されました。
「空気のにおい消しの2つの商品ブランド」の比較や、
「インスタントの2つのレトルトパックメーカ」のWebサイトの比較など、
普段は何気なくTVコマーシャルなどで見ているブランドイメージ
について、鋭く指摘してくださいました。

また、畑中氏は、学生からのリクエストのあった、
「食品ブランド、コーヒーチェーン、
デパート、衣料品メーカ、コンビ二」
などのそれぞれの企業のブランディング戦略についても臨機応変に
コメントされました。
突然、学生が口にしたブランド名について、ご存じの知識を
披露される畑中氏の雑学ぶり(雑学ではなく知識と呼ぶべきかも)
に、学生も私も感心しました。

お忙しい中、本当にありがとうございました。
来年も、来ていただけることを希望していますので、どうぞよろしくお願いします。
報告 吉田智子
2013年06月17日
教員紹介 吉田 智子

皆さん、こんにちは。
人間文化学科の教員の自己紹介シリーズの2人目は、
私、吉田 智子(よしだともこ)です。私は今年度、
人間文化学部の学部長 (人間文化学科の学科長)を
担当しています。
専門領域は、広くは「情報社会について」ですが、
特に、無料でネットから入手できるソフトウェアとして、
インターネット社会にはなくてはならない存在である
「オープンソース・ソフトウェア」について、
研究したり、普及の意味を考察したりしています。
右の写真は、Firefox OS というオープンソース・ソフトウェアが
搭載されたスマホで、これから日本語が入力できる環境が
整備されるものです。(このOSの日本語入力環境を開発されている、
オムロンソフトウェアの展示会ブースで、写真を撮らせていただきました。)

ちなみに、Google Chrome というWebブラウザも、
スマホのOSとして有名なAndroid も、
オープンソース・ソフトウェアです。
そして、もう一つの研究テーマが、
「中高生や文系学生へのプログラミング教育」
で、今年度からは科学研究助成金をもらっています。

そのプログラミング教育に使えないかと検討しているのが、
5月29日のブログでも紹介した、Raspberry Pi です。
超小型で安価なパソコンの可能性にワクワク
http://notredameningen.kyo2.jp/d2013-05-29.html
私が実行委員長をして、8月2日、3日に京都で開催される
OSC(オープンソース・カンファレンス)にも、このパソコンは
展示される予定ですので、興味のある方は、OSCへ!
OSC 2013 Kansai@Kyoto
http://www.ospn.jp/osc2013-kyoto/

この35ドルの手のひらサイズのパソコンは、HDMIケーブルや
RCAケーブル(黄色い線)でテレビ画面に接続できるのですが、
私の研究室内には、この口を持つテレビがない・・
ということで、ゼミ生といっしょに、私の研究室の壁に、
プロジェクターで投影して、壁をテレビ代わりにして
みました。
無事、起動メッセージが壁に流れ始めたときは、
拍手がおこりました。ちなみにこのパソコン、OSとしては、
オープンソース・ソフトウェアのLinuxが動いています。
3回生ゼミ生(6人中2人)との写真では、一番左が私です。
最後の写真は、私のかわいいゼミ生たち(3年生と4年生)です。

こんな風に、人間文化学部 人間文化学科では、
教員と学生の距離が近く、和気あいあいと楽しく研究活動をしています。
報告 吉田智子
2013年06月16日
公開講演会のスタッフとして・・
人間文化学科では、6月8日(土)に「アラビアンナイトと北アフリカの物語」
と題する、公開講演会を実施しました。
当日は、200名もの来場者があり、大好評でした。
その日の報告(写真つき)は、以下の大学のページで見れます。
http://www.notredame.ac.jp/news/2013/news20130612_1/news20130612_1.html
この日は、本学の学生も多く講演会を聞きに来てくれたのですが、
スタッフとして活躍してくれた学生さん、院生さんもいました。

ユニソン会館入口の「一般受付」、
「学生受付」での来客者対応から、
講演者の著書の販売まで、
きびきびと働いて下さる様子に、
教員として感動しました。

お疲れ様でした。&ありがとうございました。
報告 吉田智子
と題する、公開講演会を実施しました。
当日は、200名もの来場者があり、大好評でした。
その日の報告(写真つき)は、以下の大学のページで見れます。
http://www.notredame.ac.jp/news/2013/news20130612_1/news20130612_1.html
この日は、本学の学生も多く講演会を聞きに来てくれたのですが、
スタッフとして活躍してくれた学生さん、院生さんもいました。

ユニソン会館入口の「一般受付」、
「学生受付」での来客者対応から、
講演者の著書の販売まで、
きびきびと働いて下さる様子に、
教員として感動しました。

お疲れ様でした。&ありがとうございました。
報告 吉田智子
2013年06月13日
「陶板名画の庭」へ見学してきました
6月6日、蒸し暑い梅雨空の中で、野田と朱の「基礎演習」クラスは大学の近所にある「陶板名画の庭」に行ってきました。地上から地下へ世界の名画で飾られたコンクリートの回廊のところどころに滝と浅い池が配置されています。名画を見ながら、徐々に地下へと誘導され、地下に到着すると、滝の流れる全景を脇に、原寸大のミケランジェロの「最後の審判」が目の前に迫ってきて、思わず息を呑んでしまいました。さすが安藤忠雄さんの作品で、レプリカとは言え、滝、名画、緑陰、池、コンクリートとの絶妙な調和を見せてくれました。
短い間に、世界の名画を一覧出来るのはある意味では非常に贅沢な事だと思います。文化の香り漂う京都でこそ出来る優雅な学習ではないかとついつい思ってしまいました。
学生たちも感想文を寄せてくれましたので、写真と共に紹介致します。(朱鳳)

WMさん
今日は美術館に行き、様々な絵を見ることが出来て良かったです。私は普段、あまり美術館には行かないので、見たことが無い絵ばかりで大変新鮮でした。また、美術館と言ったら、建物の中で見ると言う感じもありましたので、今日のように外で見るのも新鮮に感じました。
私が見た中で1番記憶に残っているのは、「最後の審判」です。あのような、大きな絵は中々、見ることが出来ないと思うので見ることが出来て良かったです。また、「最後の晩餐」はインターネットで画像は見たことがありますのが、今日のように実際に美術館に行き見るのは初めてだったので、見ることが出来て良かったです。
他にも「睡蓮・朝」「テラスについて」「清明上河図」「鳥獣人物戯画」「糸杉と星の道」「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」等、初めて見るものばかりで色使いが綺麗だなと思いました。美術館の大きさは思ったより小さかったですが、中の雰囲気も良く、見たことがない絵が見ることが出来たので行けることが出来て良かったです。
YKさん
基礎演習で美術館に行ってみて、いい経験になったと思います。特に印象に残ったのは、物語になっている絵です。長い絵だけれど、どこを見ても細かく描写され、とても興味深かったです。よく見ないと分からないけれど、人の表情から動物の動きなど、変化が出ていて面白かったです。また壁一面に描かれた天国と地獄を表した絵も、助けを求める人たちの顔の険しい表情と、天国の穏やかな表情の差が見られ、やはり現世で良い行いをしないといけないということが伝わってきました。
今回で建物もとても綺麗な美術館が近くにあることが分かったので、また利用したいと思いました。

SSさん
京都府立陶板名画の庭」に行ったのは、初めてだったのでおもしろかったです。
しかも、その場所は、絵画が全て外に飾られていていたので、他の美術館とはま
た違って驚きました。ですが、外で作品をみるというのも中で作品を見ることと
また雰囲気や感じ方も違い、新鮮に感じました。
展示されている作品は7つだけで他の美術館と比べると展示数は少なく感じまし
たが、一つ一つの作品の展示の仕方にとてもこだわっていて、作品の良さと迫力
が伝わってきて、感動しました。
知っている作品も3つありました。その中でも特に、レオナルド・ダヴィンチの
「最後の晩餐」という作品は、私が通っていた高校もノートルダムでキリスト
教であったことから、よく耳にすることもありました。
聖書に「最後の晩餐」が行われた時の様子についての文章が書かれていましたし、
毎年行われていた「学校の創立記念日」の際にも「感謝のミサ」があり、司教様
が感謝の言葉を述べられ、私たちも祈るときに、必ずその様子について話されて
いたので、その作品には特に馴染みが深くありました。なので、実物を見ること
ができてよかったです。
またもう一度、改めて「京都府立陶板名画の庭」を訪れてみたいなと思いました。
NYさん
安藤忠雄さんの美術館は、本当に素晴らしいと思いました!
「最後の晩餐」とか、見れてすごかったです!
あと、最後の1番大きいいろんな意味のある絵(「最後の審判」)はなんか感動しました!
WSさん
京都府立陶板名画の庭に授業で初めて行きました。私は安藤忠雄さんが好きなので、ずっと行きたかったところなのでとても楽しみにしていました!
そして、まず入ってみると普通の美術館みたいな感じとは違う雰囲気が醸し出されていて、不思議な感覚になりました。水の中に絵があったりして神秘的でした。あと、高校生の時に歴史で習った「鳥獣戯画」が壁にずらっと貼られていて面白かったです。晴れていたのですごく安藤さんの設計が、活かされていて綺麗に美術品とマッチしていました。まず美術館なのに野外にあるのも新鮮だと思います。「最後の審判」の絵とか大きくて盛大で残酷な絵でしたが、見入ってしまう魅力がありました。
帰りには先生方にアイスをごちそうになり、とても楽しい課外授業でした。ありがとうございました。
SJさん
陶板名画の庭へ行って、一番心に残った絵は、鳥羽僧正の「鳥獣人物戯画」です。
日本最初の擬人化絵の漫画だと高校の授業で聞いたとき、ぜひ一度見てみたいと
思っていました。実際に見てみてまず、昔にも「オタク」がいたのかなと思いま
した。私は擬人化絵が好きなのでよくイラスト検索をします。そして、動物やス
イーツの擬人化を見て楽しんでいます。昔にも私のようなオタクがいたのかと思
うと親近感がわきます。もしいたのなら、話してみたいなと思いました。
次に心に残っているのがゴッホの「糸杉と星の道」です。私は中学生だったころ
美術部に所属していました。その時の文化祭でゴッホの「星月夜」を大きなキャ
ンバスに模写しました。とても大変で、絵の具を何度も買い足しに行ったのを覚
えています。しかし、ゴッホの絵をよく見るとてもいい機会になりました。私は
ゴッホの描くあの独特のうねりや色使いが好きです。
いろんな色を使ってかき上げられた作品は見る距離によって色が違って見えます。
ドット絵を近くで見たり、離して見たりするのと同じ感覚です。そんな楽しみ方
もできる絵は、やっぱりすごいなと思いました。
いろんな作品を見て、さらに大きな美術館へ行きたくなりました。また機会があ
れば、ひっそり一人で行きたいと思います。
SAさん
都府立陶板名画の庭へ行き、「最後の審判」を見て、写真などで見ると大きさが分
かりにくく、どうしても小さく思えるので、ほぼ実物と同じぐらいの大きさの絵が、
こんなに大きいのかと驚きました。
また、「鳥獣人物戯画」を見た時には、高校の時使っていた古典の教科書の表紙と同
じ絵があり、この絵から引っ張って来たんだなと思いました。
このフィールドワークを通じて、いろいろな展示に興味を持てたと思いました。
個人的には、一昨年行った正倉院展に、家族とまた行きたいと思っています。
YAさん
家の近くにある場所にもかかわらず、今まで訪れたことがなかった場所である
がなかなかに楽しめた。絵が展示してあるけれど美術館という感じではなく、外
に絵がただただ飾ってある光景はなんだか不思議である。
特に圧巻だったのは「最後の晩餐」だ。大きい分、細かいところまでしっかり
と見ることができ、教科書で見るよりも詳しく状況を知ることができた。もちろ
んその絵だけではなく、その他の絵も魅力的である。実際にはなかなか見る機会
がないであろう「鳥獣戯画図」も、近くから観察すると筆の入りなどの見落としてし
まいがちな部分がよくわかった。
よくよく調べてみると、陶板名画の庭は世界初の「屋外で鑑賞できる絵画庭園」
であるらしい。画自体は全部で8点と少々物足りないような気がしたものの、ち
ょっとした散歩気分でぼんやり見るのにはちょうどいいのかもしれない。建物の
構造自体にもこだわりが見られ、先に進むワクワク感があった。そして水音も耳
に心地よい。
学校の、そして家の近くにこんな場所があると知れて本当に良かったと思う。
今後も時間があるときはぜひ足を運んでみたい。
SKさん
今回のフィールドワークは楽しかったです。そのような大きい絵を見るのは初めてです。絵についてあまり知りませんが、面白かったと思います。最も印象に残っているのはレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」です。中学のとき、教科書で見たことがありま。中学校はキリスト教で、毎週一回バイブルを読みながら、イエスについてのことを勉強していました。そのとき、先生がこの絵のことを教えてくださいました。見られて、よかったと思います。
それから、「清明上河図」も印象に残っています。それも見たことがあります。何年前、学校のフィールドワークでアニメーションの「清明上河図」見に行きました。アニメーションの「清明上河図」は朝、昼、夜、それぞれの様子を表しました。さらに、人の話す声や水の音などもあります。とても面白かったです。アニメーションと音声があって、そのときの生活や風俗などがわかりやすいです。しかし、そのとき、人が多くて、遠くて、あまり見られませんでした。今回はゆっくり見ることができて、よかったと思います。
最後は先生方がアイスを買ったくださって、本当にありがとうございます。もし今度そのようなフィールドワークがあって、いいと思います。みんなと交流できるし、勉強もできます。そして、みんなと一緒に出掛けて、話したり、遊んだりして、楽しいと思います。
短い間に、世界の名画を一覧出来るのはある意味では非常に贅沢な事だと思います。文化の香り漂う京都でこそ出来る優雅な学習ではないかとついつい思ってしまいました。
学生たちも感想文を寄せてくれましたので、写真と共に紹介致します。(朱鳳)
WMさん
今日は美術館に行き、様々な絵を見ることが出来て良かったです。私は普段、あまり美術館には行かないので、見たことが無い絵ばかりで大変新鮮でした。また、美術館と言ったら、建物の中で見ると言う感じもありましたので、今日のように外で見るのも新鮮に感じました。
私が見た中で1番記憶に残っているのは、「最後の審判」です。あのような、大きな絵は中々、見ることが出来ないと思うので見ることが出来て良かったです。また、「最後の晩餐」はインターネットで画像は見たことがありますのが、今日のように実際に美術館に行き見るのは初めてだったので、見ることが出来て良かったです。
他にも「睡蓮・朝」「テラスについて」「清明上河図」「鳥獣人物戯画」「糸杉と星の道」「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」等、初めて見るものばかりで色使いが綺麗だなと思いました。美術館の大きさは思ったより小さかったですが、中の雰囲気も良く、見たことがない絵が見ることが出来たので行けることが出来て良かったです。
YKさん
基礎演習で美術館に行ってみて、いい経験になったと思います。特に印象に残ったのは、物語になっている絵です。長い絵だけれど、どこを見ても細かく描写され、とても興味深かったです。よく見ないと分からないけれど、人の表情から動物の動きなど、変化が出ていて面白かったです。また壁一面に描かれた天国と地獄を表した絵も、助けを求める人たちの顔の険しい表情と、天国の穏やかな表情の差が見られ、やはり現世で良い行いをしないといけないということが伝わってきました。
今回で建物もとても綺麗な美術館が近くにあることが分かったので、また利用したいと思いました。


SSさん
京都府立陶板名画の庭」に行ったのは、初めてだったのでおもしろかったです。
しかも、その場所は、絵画が全て外に飾られていていたので、他の美術館とはま
た違って驚きました。ですが、外で作品をみるというのも中で作品を見ることと
また雰囲気や感じ方も違い、新鮮に感じました。
展示されている作品は7つだけで他の美術館と比べると展示数は少なく感じまし
たが、一つ一つの作品の展示の仕方にとてもこだわっていて、作品の良さと迫力
が伝わってきて、感動しました。
知っている作品も3つありました。その中でも特に、レオナルド・ダヴィンチの
「最後の晩餐」という作品は、私が通っていた高校もノートルダムでキリスト
教であったことから、よく耳にすることもありました。
聖書に「最後の晩餐」が行われた時の様子についての文章が書かれていましたし、
毎年行われていた「学校の創立記念日」の際にも「感謝のミサ」があり、司教様
が感謝の言葉を述べられ、私たちも祈るときに、必ずその様子について話されて
いたので、その作品には特に馴染みが深くありました。なので、実物を見ること
ができてよかったです。
またもう一度、改めて「京都府立陶板名画の庭」を訪れてみたいなと思いました。
NYさん
安藤忠雄さんの美術館は、本当に素晴らしいと思いました!
「最後の晩餐」とか、見れてすごかったです!
あと、最後の1番大きいいろんな意味のある絵(「最後の審判」)はなんか感動しました!
WSさん
京都府立陶板名画の庭に授業で初めて行きました。私は安藤忠雄さんが好きなので、ずっと行きたかったところなのでとても楽しみにしていました!
そして、まず入ってみると普通の美術館みたいな感じとは違う雰囲気が醸し出されていて、不思議な感覚になりました。水の中に絵があったりして神秘的でした。あと、高校生の時に歴史で習った「鳥獣戯画」が壁にずらっと貼られていて面白かったです。晴れていたのですごく安藤さんの設計が、活かされていて綺麗に美術品とマッチしていました。まず美術館なのに野外にあるのも新鮮だと思います。「最後の審判」の絵とか大きくて盛大で残酷な絵でしたが、見入ってしまう魅力がありました。
帰りには先生方にアイスをごちそうになり、とても楽しい課外授業でした。ありがとうございました。
SJさん
陶板名画の庭へ行って、一番心に残った絵は、鳥羽僧正の「鳥獣人物戯画」です。
日本最初の擬人化絵の漫画だと高校の授業で聞いたとき、ぜひ一度見てみたいと
思っていました。実際に見てみてまず、昔にも「オタク」がいたのかなと思いま
した。私は擬人化絵が好きなのでよくイラスト検索をします。そして、動物やス
イーツの擬人化を見て楽しんでいます。昔にも私のようなオタクがいたのかと思
うと親近感がわきます。もしいたのなら、話してみたいなと思いました。
次に心に残っているのがゴッホの「糸杉と星の道」です。私は中学生だったころ
美術部に所属していました。その時の文化祭でゴッホの「星月夜」を大きなキャ
ンバスに模写しました。とても大変で、絵の具を何度も買い足しに行ったのを覚
えています。しかし、ゴッホの絵をよく見るとてもいい機会になりました。私は
ゴッホの描くあの独特のうねりや色使いが好きです。
いろんな色を使ってかき上げられた作品は見る距離によって色が違って見えます。
ドット絵を近くで見たり、離して見たりするのと同じ感覚です。そんな楽しみ方
もできる絵は、やっぱりすごいなと思いました。
いろんな作品を見て、さらに大きな美術館へ行きたくなりました。また機会があ
れば、ひっそり一人で行きたいと思います。
SAさん
都府立陶板名画の庭へ行き、「最後の審判」を見て、写真などで見ると大きさが分
かりにくく、どうしても小さく思えるので、ほぼ実物と同じぐらいの大きさの絵が、
こんなに大きいのかと驚きました。
また、「鳥獣人物戯画」を見た時には、高校の時使っていた古典の教科書の表紙と同
じ絵があり、この絵から引っ張って来たんだなと思いました。
このフィールドワークを通じて、いろいろな展示に興味を持てたと思いました。
個人的には、一昨年行った正倉院展に、家族とまた行きたいと思っています。
YAさん
家の近くにある場所にもかかわらず、今まで訪れたことがなかった場所である
がなかなかに楽しめた。絵が展示してあるけれど美術館という感じではなく、外
に絵がただただ飾ってある光景はなんだか不思議である。
特に圧巻だったのは「最後の晩餐」だ。大きい分、細かいところまでしっかり
と見ることができ、教科書で見るよりも詳しく状況を知ることができた。もちろ
んその絵だけではなく、その他の絵も魅力的である。実際にはなかなか見る機会
がないであろう「鳥獣戯画図」も、近くから観察すると筆の入りなどの見落としてし
まいがちな部分がよくわかった。
よくよく調べてみると、陶板名画の庭は世界初の「屋外で鑑賞できる絵画庭園」
であるらしい。画自体は全部で8点と少々物足りないような気がしたものの、ち
ょっとした散歩気分でぼんやり見るのにはちょうどいいのかもしれない。建物の
構造自体にもこだわりが見られ、先に進むワクワク感があった。そして水音も耳
に心地よい。
学校の、そして家の近くにこんな場所があると知れて本当に良かったと思う。
今後も時間があるときはぜひ足を運んでみたい。
SKさん
今回のフィールドワークは楽しかったです。そのような大きい絵を見るのは初めてです。絵についてあまり知りませんが、面白かったと思います。最も印象に残っているのはレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」です。中学のとき、教科書で見たことがありま。中学校はキリスト教で、毎週一回バイブルを読みながら、イエスについてのことを勉強していました。そのとき、先生がこの絵のことを教えてくださいました。見られて、よかったと思います。
それから、「清明上河図」も印象に残っています。それも見たことがあります。何年前、学校のフィールドワークでアニメーションの「清明上河図」見に行きました。アニメーションの「清明上河図」は朝、昼、夜、それぞれの様子を表しました。さらに、人の話す声や水の音などもあります。とても面白かったです。アニメーションと音声があって、そのときの生活や風俗などがわかりやすいです。しかし、そのとき、人が多くて、遠くて、あまり見られませんでした。今回はゆっくり見ることができて、よかったと思います。
最後は先生方がアイスを買ったくださって、本当にありがとうございます。もし今度そのようなフィールドワークがあって、いいと思います。みんなと交流できるし、勉強もできます。そして、みんなと一緒に出掛けて、話したり、遊んだりして、楽しいと思います。
2013年06月09日
教員紹介 長沼光彦
皆さん、こんにちは。 
今日は、人間文化学科の教員である私、
長沼光彦、の自己紹介をいたします。
(写真の一番右が私です。)
大学の教員は、
持続的に調べたり考えたりする、
専門分野を持っています。
私の専門分野は、
日本の近現代文学です。
芥川龍之介、谷崎潤一郎ら、
大正・昭和期に活躍した小説家や、
中原中也ら、詩人の研究をしています。
特に、その時代の思想や風俗など、
文化的背景と作品を結びつけて、
考察しています。
研究したり考えたりした内容は、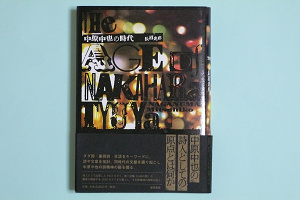
『中原中也の時代』(笠間書院、2011)
などの本や、
「「細雪」の京都 ―遊山する都市」
(『比較古都論』2013)
などの論文にまとめたり、
学会で発表したりします。
〔*人間文化学科では、
教員それぞれの研究を紹介した
ブックレットを 発行しています。
興味があれば、ご連絡ください。〕
私が担当している授業は、
「国文学概論」や「日本文学」など、
研究している
日本文学の講義はもちろんのこと、
「ホスピタリティ京都」や
「日本語コミュニケーション」など、
京都をはじめとした日本文化や、
日本語の表現に、
関わる講義もしています。
文学は、表現の工夫や、
人物の思想などに注目すると、
深読みもでき、
繰り返し楽しむことができます。
大学に入って、
本格的に読解法を学んでみるのも、
良いでしょう。
また、日本語の表現力は、社会人になれば、
どこでも求められる能力ですから、
大学生になったら、
ぜひ身につけてほしいですね。
さらに、「編集倶楽部」という、
将来の仕事をイメージしたゼミ
(キャリア実践ゼミ)や、
授業外の京都フィールドワーク活動
(北山探検隊)、
映像表現の鑑賞会
(放課後シネマ倶楽部)
などの活動もお手伝いしています。
学生の皆さんのやる気があれば、
実践する機会をどんどん作ってほしい
と思っています。
その活動のいくつかは、
このブログでも紹介いたしました。
他の記事もご覧いただき、
人間文化学科の活動を知っていただければ、
嬉しいですね。
〔最後の写真は、
フィールドワークに出かけたとき、
夕暮れの琵琶湖畔で、
学生が私を撮影したものです。〕
報告 長沼光彦

今日は、人間文化学科の教員である私、
長沼光彦、の自己紹介をいたします。
(写真の一番右が私です。)
大学の教員は、
持続的に調べたり考えたりする、
専門分野を持っています。
私の専門分野は、
日本の近現代文学です。
芥川龍之介、谷崎潤一郎ら、
大正・昭和期に活躍した小説家や、
中原中也ら、詩人の研究をしています。
特に、その時代の思想や風俗など、
文化的背景と作品を結びつけて、
考察しています。
研究したり考えたりした内容は、
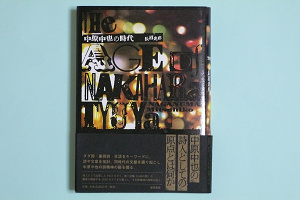
『中原中也の時代』(笠間書院、2011)
などの本や、
「「細雪」の京都 ―遊山する都市」
(『比較古都論』2013)
などの論文にまとめたり、
学会で発表したりします。
〔*人間文化学科では、
教員それぞれの研究を紹介した
ブックレットを 発行しています。
興味があれば、ご連絡ください。〕
私が担当している授業は、
「国文学概論」や「日本文学」など、
研究している
日本文学の講義はもちろんのこと、

「ホスピタリティ京都」や
「日本語コミュニケーション」など、
京都をはじめとした日本文化や、
日本語の表現に、
関わる講義もしています。
文学は、表現の工夫や、
人物の思想などに注目すると、
深読みもでき、
繰り返し楽しむことができます。
大学に入って、
本格的に読解法を学んでみるのも、
良いでしょう。
また、日本語の表現力は、社会人になれば、
どこでも求められる能力ですから、
大学生になったら、
ぜひ身につけてほしいですね。

さらに、「編集倶楽部」という、
将来の仕事をイメージしたゼミ
(キャリア実践ゼミ)や、
授業外の京都フィールドワーク活動
(北山探検隊)、
映像表現の鑑賞会
(放課後シネマ倶楽部)
などの活動もお手伝いしています。
学生の皆さんのやる気があれば、
実践する機会をどんどん作ってほしい
と思っています。
その活動のいくつかは、
このブログでも紹介いたしました。

他の記事もご覧いただき、
人間文化学科の活動を知っていただければ、
嬉しいですね。
〔最後の写真は、
フィールドワークに出かけたとき、
夕暮れの琵琶湖畔で、
学生が私を撮影したものです。〕
報告 長沼光彦
2013年06月02日
ビジネス文書:実務者から伺うことで実感!
ビジネス文書を学生時代に学ぼうとしても、実体験がないためイメージがわきにくい。
そのため、授業に出てきていても、なんとなくの学習になってしまいがち。

そこで、人間文化学科の授業「ビジネスライティング」では、
学習の早い段階で、実務者から直接話を伺って学習を進める方法をとっている。
実務者が普段から気をつけていること、思い、具体的な方法など、
直接話を伺うことで、
今まで見えなかった現場のイメージが、いくらか見えてくる。

その結果、今、何をするべきか、どのようなことに留意して学習をしていけばいいのかなどが見えてくる。
同じ学習をするのでも、実務をイメージできるかどうかで、全く中身はちがっているはず!
本年も昨年同様、二人の実務者(ゲスト)をお迎えし、
10人前後のグループに分かれて、お話を伺った。
ビジネスの雰囲気を少しでも出すため、違う教室に、各グループの担当者がゲストを案内した。
もちろんビジネスマナーを意識して。

そして、見様見真似の「依頼書」作成経験などを踏まえ、
各グループの司会担当者のもと質問をしながら、ゲストにお話を伺った。
「とても丁寧に答えてくださったので、良い経験となりました。
ビジネス文書を書くことはとても神経を使うことなんだなと思いました」
「『もう少し敬語に関心をもってみては?』
という言葉が印象に残っています。
私たちの敬語が話せない面に対して批判的に言うのではなく、
素直に受け止めることができました」
「実際にビジネス文書を作成していらっしゃるからこその意見が聞けて
貴重な体験となりました」
などの感想がみられるとおり、
ビジネス文書といっても、ただ書けばいいものではないことなど、
深く理解してもらえたことでしょう。
さあ、ここまでくれば、あとはスキルを身につけるだけ。
身につけるべきことはしっかり身につけてしまいましょう!
報告 平野美保
2013年06月01日
能の魅力を知る:金剛流能楽師・今井克紀先生
人間文化学科1年次生必修科目「基礎演習」は、
10人以下の少人数クラスで、大学の学びの基礎を習得する科目ですが、
一 年に4回、合同クラスの特 別講義を実施しています。
各方面で活躍されている著名な先生方をお招きし、
文化について、よ り深く、多角的に学んでもらうことがねらいです。
これまで、琴古流尺八奏者の岡田道明先生、
和紙デザイナーの堀木エリ子先生、
絵本作家の永田萠先生など、さまざまな分野 の先生方をお迎えして、
学生たちの興味・関心が広がり深まる、貴重なお話を多々うかがってきました。

さて、今年第一回目は、
金剛流能楽師・今井克紀先生による
「能の魅力を知る~面白さを体験してみよう~」と題する授業で した。
最初の30分は、ホワイトボー ド、パワーポイント、DVDなどを用いた講義です

能がどのようにして生まれ、どのように発展して
「四座一流(金剛、金 春、観世、宝生と喜多)」として現代まで継承されてきたか、
その歴史について分かりやすく解説して下さいました。
義満、信長、秀吉、家康、秀 忠といった武将たちが
能の発展に大きく関与していたというお話に、歴女たちの目が輝きます。
その後、金剛能楽堂の写真を拝 見しながら、
能舞台の造りや意味について、お話下さいました。

能は本来、神に奉納するために神前で行うものなので、
浄瑠璃や歌舞伎と違って緞帳はない、シテが登場する所にある揚げ幕は、
あの世(鏡の間)とこの世(舞台)とを隔てるための もので、
あの世からこの世に渡る細い廊下のようなところを橋掛かりという、などなど、
演劇と言えばミュージカ ルぐらいしか見たことのない現代っ子たちにとって、興味深いお話でした。
ご講義のあとは、実技です。
ま ずは謡。
詞章が配られ、先生のお手本を拝聴します。
曲は、世阿弥の名作「羽衣」で す。
天人が奪われた羽衣を取り返すため、舞いを舞って、天に帰って行くという話。
謡ったのは、次の一節です。
迦陵頻伽(かりょうびん が)の馴れ馴れし、迦陵頻伽の馴れ馴れし、声今更に僅かなる、雁がねの帰りゆく、天路を聞けばなつかしや、千鳥鴎の沖つ波、行 くか帰るか春風の、空に吹くまでなつかしや、空に吹くまでなつかしや。
先生が謡いを始められたとたん、空気が変わりました。
今まで何となく弛緩していたムードが一気にぴんと引き締まったのです。
学生たちの背筋が伸びた ように見えました。
何百年と磨き上げられてきた伝統の威力を目の当たりにした気がします。

その後、先生の後について、謡 う練習をしました。
独特の抑揚があり、そう簡単なものではありません。
喉から声を出すだけでは、先生のような 声は出しえないことを実感します。
さて次は、仕舞の実践です。
物 語の末尾、天人が天翔(あまがけ)り天に帰っていくシーンで、
扇を羽のように使いながら舞います。
東遊びの数々に、東遊び の数々に、その名も月の色人は、三五夜中の空にまた、満月真如の影となり、御願円満国土成就、七宝充満の宝を降らし、国 土にこれを施し給ふ、さるほどに、時移って天の羽衣、浦風にたなびきたなびく、三保の松原浮島が雲の、愛鷹山や富士の高嶺、かすか になりて、天つ御空の霞に紛れて失せにけり。

20人ずつくらい、中啓(扇)を手に持ち登場、先生の振りを見よう見まねで、舞います。
途中「七宝充満の宝を降らし」の ところで、中啓を招くように用いるのですが、
先生が「ゴールデンボンバーのように」と仰ったので、学生たちも 俄然調子に乗ってきました。
やはり体を動かして学ぶのは楽 しいようで、
終始笑顔で、初の仕舞体験を楽しませていただきました。
最後に、先生が能面をつけて、今 舞ったところの模範演技をお見せ下さいました。
謡いながら舞うことの難しさを想像しながら、みんな喰い入るような目で見 つめていました。
日本伝統芸能の奥深さを身をもって学ばせていただきました。
今井先生、ありがとうございました。

以下、受講した学生たちの感想 です。
WAさん
実際に間近で能について、話を聞かせていただき、とてもおもしろく興味深かったです。
意外と動きが多く、ハー ドなんだと知りました。
動きと声の両方なので、一種の運動のようで、私だとすぐに息が上がりそうだと思いました。
プリ ントもあったので、謡の内容も理解できて、楽しかっ たです。

KTさん
仕舞いを習ってみて、一つ一つの動作に意味があることを初めて知りました。
見ているだけだと、あまり難しさ が分からなかったけれど、 やってみるととても大変でした。
動きだけでも習得するのに時間がかかりそうなのに、
言葉をつ けたらさらに難易度が上がるだろうなと、実感しまし た。
FEさん
能を実際に見たのは初めてでした。
舞台の構造があの世とこの世だということも初めて知りました。
お面が角度 によって笑って見えたり怖 く見えたりして、
私は正直あのお面が怖くて苦手なのですが、おもしろかったです。
声を出すのも大変でし たが、今井先生の声はやはり美しいなと思い ました。

MYさん
先生が普通にお話をされる時のお声と、能の時のお声がまったく違ったので、とても驚きました。
私は滋賀県の 守山に住んでいて、市民 ホールはすぐ近くなのに、
地元を舞台にした能についての取り組みがあったなんて、全然知りませ んでした。
今度是非その「望月」を見に行ってみたい なと思いました。
OMさん
能について、あまり見たことはなかったので、今日詳しくお話を聞いて、とても興味がわきました。
能が平安時代から始まり、今まで続い ていること、
そしてそれを受け継いできた人たちがいることに感動しました。

KMさん
高校で能を見に行ったことがあり、授業でも詳しく学んだのですが、
能楽師の方から直接その歴史や文化のお話 をうかがい、
能の奥深さを いっそう感じることができました。
また、実際に謡や仕舞のご指導をいただく体験ができ、
と ても貴重な時間を過ごせて、よかったです。
MYさん
実際体験してみて、扇の使い方がとても難しいと思いました。
また舞いながら、どういうストーリーで舞って いるのか解説いただいたので、わかりやすく楽しかったです。
貴重な体験ができて、よかったです。
報告 堀 勝博


