2016年06月20日
「平成生まれのための『Unix考古学』〜Unixとインターネットがこんなに発展したのはなぜなの?〜」
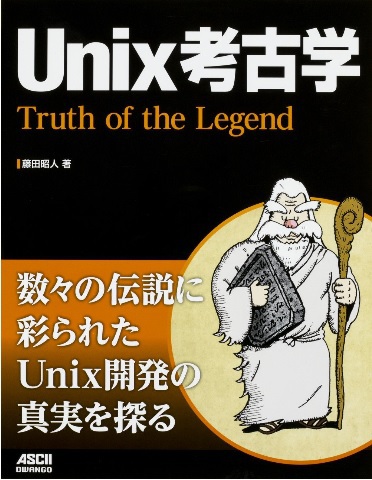
京都ノートルダム女子大学の「情報科学応用」と「ウェブデザインI」という科目名の授業(どちらも吉田智子の担当)に、6月17日(金)、スペシャルゲストが講義に来てくださいました。
スペシャルゲストとは、4月に発行された話題の書籍『Unix考古学 -The Truth of Legend-』の著者、藤田昭人さんです。
藤田さんは、今年のオープンソースカンファレンス京都( http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/ 2016/07/29,30 実施)で、基調講演をして下さる方で、関東に住んでおられます。
が、この日の夕方、この大学で行われるオープンソースカンファレンスのローカルスタッフミーティングに合わせて、京都に来てくださったので、私の授業での講義もお願いしたというわけでした。

ずいぶん前のことになりますが、藤田さんは私がUnixワークステーション開発の部署でOLをしていた頃の、Unixの師匠でもあります。(藤田さんは、私のことを「昔の同僚です」って紹介されましたが、師匠と弟子という方が私にはぴったりきます。)
まず1時間目の「情報科学応用」では、ちょうどコンピュータでの日本語環境を学ぶ初回だったので、
「コンピュータで日本語が使えるようになるということ」
というテーマでの講義をお願いしました。
藤田さんは1990年代に数年間、会社からの派遣で Omron LUNA-88K を40台寄贈したカーネギーメロン大学(ペンシルベニア州ピッツバーグ)に滞在されました。その時に、日本語が扱えるUnixマシンをサーバーにして、日本人滞在者へ情報を提供する「ピッツバーグ便利帳」という日本語の情報提供のサーバー環境を作って運用されていた話など、いろいろな具体的な例を紹介してくださいました。
ピッツバーグ便利帳 https://sites.google.com/site/pghbenricho/
長年に渡って、日本人はコンピュータで日本語を扱うことができるように努力してきたんですよね。私はそれを見てきた世代なので、そうそう、という感じで聞けましたが、平成生まれの学生さんはどうなんだろう?と思ったところで、藤田さんが、「この中で、留学などで海外に滞在したことがある人はいますか?」と聞かれました。
日本にいる限り、日本語が扱えないコンピュータ(PC、スマホなど)に出会うことがない若い学生の中でも、海外留学した時の現地のPC環境を経験したことがあると、日本語環境の話は理解しやすかったようです。
次の、2時間目の「ウェブデザインI」の授業では、
「平成生まれのための『Unix考古学』〜Unixとインターネットがこんなに発展したのはなぜなの?〜」
という講義タイトルでの話をお願いしました。
そして、藤田さんの講義を鋭く突っ込む役割として、平成生まれの大学生、Pasta-Kさんにも来ていただきました。

インターネットの元となった ARPAnet の話、Unixの誕生から発展の話などの中で、私が特に注目したのは、以下の話でした。
ARPAnetが成功した(インターネットという世界中を取り巻くネットワークが誕生して普及した)理由として、一番最初に掲げられるのが、BSD Unix というカリフォルニア大学バークレー校で作られたUnix の存在が大きいということ。1983年に誕生した 4.2 BSD には、TCP/IP が標準搭載されていたことにより、ARPAnetをみんなに普及させるという点で、貢献した。OSIというインターネットとは違う規格のプロトコルを電話会社は考えていて、そちらの方がより公式なプロトコルであったが、そちらではなく、インターネットが採用したTCP/IPの方が事実上の標準(デファクトスタンダード)として普及したのは、BSD Unix の貢献度が高い。
そして、重要なこととしては、BSDのソースコードをタダで世界に配って回るということが、世界での技術動向を支配する、非常に重要な意味を持ち、有効な手段であることが明らかになったのである。これはその後のオープンソースソフトウェアの活動の一番最初のひな型になった。
なるほど~。本当にその通りですね。日本人プログラマーとして、1994年リリースの4.4 BSDの開発プロジェクトに参加された藤田さんが言われると、より説得力がありました。
その後、Pasta-K さんや本学の学生からの質問にも答えていただき、学生たちにとっても有意義な時間となったと思います。

2コマ、合計3時間、お話をしていただいた後に、大学の近所のインドカレーのお店で、学生も交えてさらに情報交換。

そして夕方は、本学で実施された「オープンソースカンファレンスのローカルスタッフミーティング」で、基調講演の内容に関しての打ち合わせも行いました。こちらのミーティングには、本学の学生が2名、参加してくれました。

藤田さん、Pasta-Kさん、ノートルダムでの長~い一日、お疲れ様でした。本番の7月30日の講演を今から楽しみにしています。
以下が、2016年7月30日(土)に行われる、藤田さんのOSC京都での基調講演の概要です。
”平成生まれのための「Unix考古学」~GitHubなしでどうやって開発していたの?~”
http://www.ospn.jp/osc2016-kyoto/pdf/press_release_kyoto_20160530.pdf
報告:吉田智子
特別講義「2年次生から考える自分の未来」が開催されました
教職実践演習の授業から ―漢文を読み解くおもしろさ
深泥池・上賀茂フィールドワーク2 (令和2年12月)
深泥池・上賀茂フィールドワーク1 (令和2年12月)
お出汁の うね乃 ワークショップ体験(令和2年11月)
植物園を散策しました(令和2年11月)
教職実践演習の授業から ―漢文を読み解くおもしろさ
深泥池・上賀茂フィールドワーク2 (令和2年12月)
深泥池・上賀茂フィールドワーク1 (令和2年12月)
お出汁の うね乃 ワークショップ体験(令和2年11月)
植物園を散策しました(令和2年11月)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







